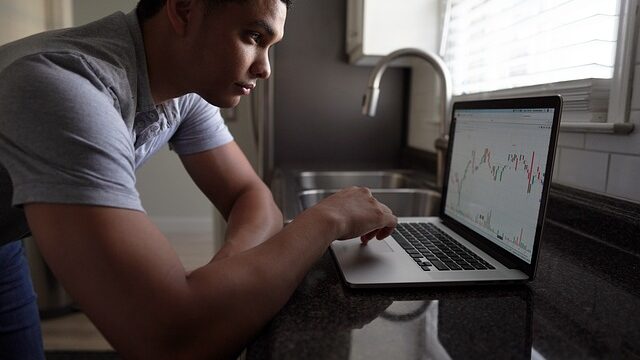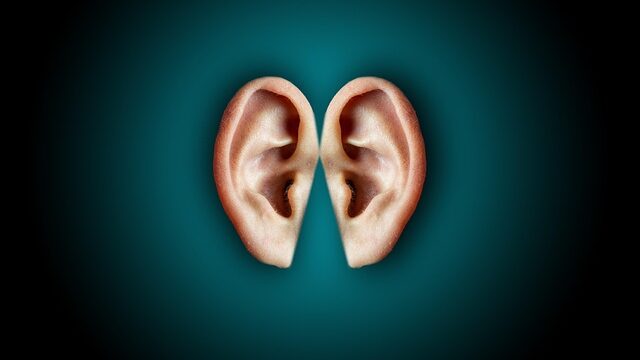「読み手に届く 文章技術」”伝わる”文章の書き方

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、文章力を上げたいと思ったからだ。「悪文の構造」もそうだが、日々の業務で議事録や報告書を作成しているので、文章力は常に向上させたいと思っている。2冊目の本として読むことにした。
読み手に届く 文章技術 (石黒圭、2025年6月、ちくまプリマー新書)
文章における最大の課題
本書では、文章における最大の課題は、「書き手の書いた文章が、読み手に理解されないこと」と書かれている。要するに「読んでも(何が書いてあるか、何が言いたいのか)さっぱり分からん・・・」というのを避けるのが目的である。
このため相手に理解されない文章を避けるための工夫や、アドバイスが述べられいる。自分の文章技術(文章力)を上げるというよりは、他人に向けて発信する技術を向上させることを主眼としている。
差分(読み手への配慮)
差分とは、書き手と読み手の知識の差である。例えば、ガンダムオタクと一般人での会話、50代と20代での漫画の会話を考えてみるとわかる。一方が「当然、知っているだろう」と思うことについて、一方は「当然、知らない」場合があるということだ。
ガンダムを見たこと無い、ドラゴンボール読んだこと無い人に、「アムロってさぁ」「フリーザ様が」と言ったところで通じるわけもない。このような知識の差については、当然書き手側が配慮する必要がある。自分が書く文章を読む人の知識がどれぐらいなのかを“想定”して書く必要があるということだ。
読み手を意識する
・一般人に読んでもらうのか
・ガンダムオタク向けの同人誌なのか
これにより、知識の前提条件が異なるので、当然書く内容にも配慮しなければならない。
書き手が一方的に好き勝手書いたところで、読み手の知識力が足りなければ、「読んでも何書いてあるか、さっぱり分からんかったわ」となる。
文章構成(料理レシピ)
文章構成が悪ければ、相手に伝わりにくい。文章構成とは、いわゆる「起承転結」である。本書では、文章構成のお手本として、料理レシピが紹介されている。確かに料理レシピは、手順であるため要領よく構成する必要がある。読み手がストレスを感じることなく目的の料理を作れたのであれば、書き手の意図は上手く読み手に伝わったことになる。
文章の並べ方を意識する
・調理方法
・材料表示
・盛り付け
・材料の仕込み
・その他注意点
意図的にバラバラに書いたが、こういった内容を手際よく順番に並べる技術が求められる。玉ねぎはみじん切りにし、次に添えるためのニンジンを〇〇切りして、最後にひき肉を□□g用意して・・・
ダラダラと長文にするのではなく、料理をしながら片手間で読むことを想像して、
①玉ねぎはみじん切り
②添え物のニンジンを〇〇切り
③ひき肉□□gを・・・
と簡素に箇条書きにするような配慮も、書き手側には求められる。
根拠(なぜそうなのか)
根拠は、小論文など相手を説得する文章に必要となる。厳密には、自分の主張に対する根拠となる。「私はこう考える。なぜなら、(根拠の提示)」の部分である。単純に自分の思い付き(主観)だけなのか、何かしらの根拠があるのかで説得力も大きく違ってくる。
根拠(理由)のない文章は後々困る
私が普段仕事で読む文章で気になるのが、この根拠の示されていない文章である。特に議事録に多い。「この件については、A案で進める」とだけ書いてある。「なぜ、A案が採用されたのか」、その根拠(理由)の書かれていない文章をよく目にする。
こういう文章は、遠い将来見返した時に、非常に悩ましいことになる。「なぜ」の部分が書かれていないので、結局は何も分からないのと同じだからだ。議事録としての機能をはたしていない。主張と根拠、結論と根拠、これらは必ずセットで記載する必要がある。
定義(曖昧だと始まらない)
定義はとても大事だ。いわゆる、「何をもって〇〇というのか?」の部分である。「お金持ち、幸せ、失敗」など、抽象的な表現に対しては、明確な定義を行わなければ話が始まらない。
もちろん「幸せってなんだろう」という“定義自体”を話題にする場合もある。しかし、「このプロジェクトは失敗したのか?」と漠然と聞かれると返事に困る場合もある。失敗の定義が明確ではないからだ。
・赤字だから失敗なのか
・黒字だが集客数、売上げが目標以下だから失敗なのか
・スケジュールを守れなかったから失敗なのか
定義次第で結論が変わってもよい
本書では、「最強の生物とは」が事例として紹介されている。これは見方(定義)により、答えがどうとでも変わって来る。
・走りの速さで最強の生物なら 例えばチーター
・腕力で最強の生物なら 例えばゴリラ
・知能で最強の生物なら 例えば人間
このように、定義次第で「最強の生物」は幾通りもある。これは、書き手が最強の生物部門を定義し、自分の主張したい結論に持っていてよいと書かれている。
まとめ
本書では、上記で紹介した内容以外にも、
・視点:1人称、3人称視点
・引用
・推敲
・配慮:親しさによる敬語の使い方
などが書かれていた。興味のある方は自分で読んでもらいたい。
文章力は必要
読みにくい文章は、本当に読んでいて苦痛である。なぜなら、こちらの脳をフル活用して、不十分な部分を補完しなければならないからである。しかも、それが間違っている可能性もある。
特に現在の業務では「情報共有」が当たり前となっている。溢れんばかりのCCメールで業務報告や議事録が大量に送られてくる。特に議事録においては、その会議に参加していなかった場合、結論だけを書かれても、なぜそうなったのかの理由(根拠)が書かれていないと非常にストレスとなる。
本書を読んで、私自身もそういった配慮が欠けている部分があるかもしれないと感じた。特に「根拠」と「定義」は非常に重要であると感じる。