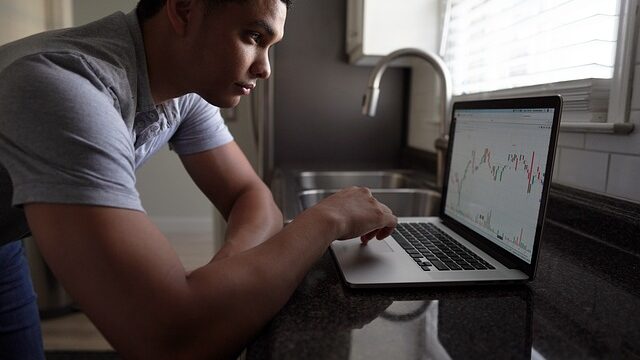「若者が去っていく職場」会社側の待遇にも限界があるんだが

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、会社で若手社員が1人辞めたからである。辞めた理由は「上司が嫌だから」という理由であった。もう少し詳細に書くと、その若手に仕事ばかり振って自分は手伝いもしない上司(課長)が嫌だったからである。私はその若手とは比較的仲が良く、辞める数か月前から色々と相談を受けていた。
このようなことがあって、今の若手社員がどのような目線で会社を見ているのか、どのような点で不満を持つのかを知りたいと思ったからである。
若者が去っていく職場(上田晶美、2025年6月、思草社)
本書を読んだ感想
本書を読んだ私の感想は、
・ある程度理解できる部分もあるが、著者の一方的に会社が悪い、古い考え方が悪いという流れに辟易する
・若手擁護一辺倒の意見が多すぎる
・著者がコンサルを名乗っている割には、現状説明ばかりで具体的な対策提案がイマイチ
と、私がおっさん側ということもあるのか、イラつく内容が多かったというのが感想である。お互いが納得できる体制を模索するというようなアドバイスがあれでいいのに、基本会社(おっさん)が悪、会社(おっさん)が悔い改めるべきというのは違うだろう。
転職の動機は複合と積み重ね
転職の動機は、ひとつではなく小さな不満がいくつも積み重なった複合的と書かれている。私の会社を辞めた若手も以下の様に、これとまったく同じことを言っていた。
・辞めるに至る致命的な理由は特に思い浮かばない
・嫌な出来事が少しずつ積み重なって辞める決意をした
・本人はこれを「ポイントカード理論」と言っていた
・不満スタンプが徐々に貯まっていき、ポイントカードがいっぱいになったので辞める
本書にある通り、この状況になってから引き留めをしても、絶対に間に合わない。会社に辞めることを言う時点で「辞めるという結果は決まっている」というのは本当にそうであった。うちの会社でも当然、説得はしたが「次の就職先が決まっていない」にも関わらず応じなかった。
会社側の対策は
私が今回若手が辞めたことから学んだのは、日々のケアが重要と言うことである。少しずつ不満がたまっていく。なので、そのような兆候が無いか、現在の状況に不満が無いかを日々観察することが必要だと感じた。
若手の8割が転職を視野に
まぁ、これは時代の流れと需要と供給の市場原理の変化によりやむを得ないことだと思う。今や共働きが当たり前なのと同じで、転職も当たり前という時代だ。だが、転職される方も、する方もお互いに相当な労力を要するのは事実だ。出来れば避けたいところである。どうすればいいのか?
本書を読んだり、ネット上での情報を見ると若者が転職する大きな理由が「事前に聞いていた話と違う」というものである。いわゆるミスマッチである。これは、企業側に非があると思う。
ミスマッチは事前回避可能
「嘘をついて採用しても、どうせすぐに本当のことを知られて、辞められるだけですよ。それならお互い時間と労力の無駄なので、会社に入れば〇〇という仕事をしてもらう」と本当のことを言いましょう、と採用面接があるごとに部長などには言っている。
出来ることと出来ないことがある
若手社員に対しては「会社側として出来ることと、出来ないこと」があることは理解してもらいたいと思う。有給MAX消化、残業一切無し、飲み会無し、上司とのいやな付き合い無し、そのような理想郷の様な会社は存在しないだろう。若手もどこかで妥協しなければならないはずだ。
若手に人気のある職場
参考までに現在の若手に人気のある職場が紹介されていた。もし自社に少しでも若者を呼び込みたいのであれば、導入を検討してみてはいかがだろうか。ただし、中小にはハードルは高いと思う。
①リモートワーク
②フリーアドレス(自由席)
③服装自由
大手企業ならまだしも、中小企業で対応できるのは③か①くらいではないだろうか。
①リモートワーク
これは職種によるとしか言えない。IT系であればリモート率は高いのだろうが、サービス業、飲食では当然無理、公官庁でも対応は厳しいだろう。私の会社でも一応リモートワークは可能な状況だが、最近はリモートワークをする人はかなり減ってきているのが現状である。
また、新卒入社後、数か月でリモートを希望と言われても、無理があるような気がする。。。若手は王様じゃないんだぞ、とおっさん根性が出てしまう。
②フリーアドレス(自由席)
このあたり、完全に外資系のイメージが先行しているように思える。ソファでノートPC片手にラフな格好で、お菓子でも食べながら仕事をしているイメージだろうか。まぁ、こちらも日本の企業で採用している所は大手IT系ぐらいなのだろうか。中小では、かなうべくもない。
③服装自由
もっとも実現のハードルが低いのがこれだろう。私の経験として他社を見渡しても、かなりの確率で服装はラフになってきている。いわゆるオフィスカジュアルの採用である。私の会社でも、今年から試験的に実施しているが非常に楽である。これは、おっさんの私としても会社の標準装備として採用して欲しいと感じるぐらいである。
若手とのコミュニケーション十箇条
おっさんが、若手とコミュニケーションを取るための十箇条として、著者から「ありがたいお言葉」が述べられていたので紹介する。
①3年で転職することを前提に
なんともね。全員がそうだとは思いたくないが。
②アンコンシャスバイアス撲滅
これは先入観を持つなということである。「自分たちもそうしてきたから、雑用は若手にやらせればいい」という考え方はNGと書かれていた。これは注意しなければならない事項だと感じる。
③ホワイト企業の定義確認
有給取得100%なんて今や当たり前なので、「ウチはホワイトだろ」とドヤるな、とのこと。心当たりのある人は注意しよう。
④上下関係は無いと考えろ
これはさすがに無理ありすぎだろと思う。組織として成立しないだろ。逆に大手ほど達成不能。
⑤作業のはじめにしっかりと説明する
これは同意。説明もなく「あれやっといて」は通用しない。
⑥テキストで伝える
これは同意。口頭だとメモしなければならない、後で言った言わないの問題に発展する、意図が正確に伝わらない等の弊害が多い。私も最近頑張って、意図的にチャットを使うようにしている。ただ、本人が横に座っているのにチャットは無理があるような気もする。
⑦ほうれんそう不要
指示を出したら後は待つだけ、との著者からのご指示。意味不明・理解不能。最後までやって間違ってたら?それこそコスパ最悪だろう。
⑧断定しない、決めつけ厳禁
まぁ、それはそうだろう。特に若者に限定なくこの考えは必要だと思うが。
⑨昔話はするな
激しく同意。「俺の若いころはな・・・」は厳禁。ダメぜったい。うちの課長がこれをやり、若手が幻滅して辞めていった。逆に考えて、辞めさせたい若手がいるなら効果は抜群である。積極的に使っていこう。パワハラにも該当しないだろう。
⑩質問しないこと
「なんでこんな失敗をするんだ?」等の問い詰めはするなとのこと。高圧的になるなということか。特に理詰めの正論攻撃はやめておこう。若手を追い込んだところで、イイことな何もない。
まとめ
この国はどこへ向かうのか
少子高齢化、担い手不足、生産性の向上と叫ばれて久しいが、なんの改善もされないままここまで来てしまった。日本が先進国と言われたのも今や昔の話になりつつある。今後この国はどこに向かうのか不安でならない。
女性、定年後のシニア等自国で動員できる生産年齢人口は、ほとんど動員しつくしている。あとは外国人労働者の受入れだが、これはドイツなどの悲惨な失敗例もあり、国民の感情的抵抗がある。
会社が気に食わなければ辞めればいいという考えも、今の時代では常識なのかもしれない。だが、団塊世代は引退し、団塊ジュニア世代の引退も近づいている。これからこの国を担っていく若手には、豊かな日本を維持するためにも、個人の技術力は身に着けて欲しいと切に願う。
こういうことを書くと、若手への押し付けだといわれるかもしれないが、時の流れに従い誰が押し付けなくてもバトンは自然と回って来るのだ。