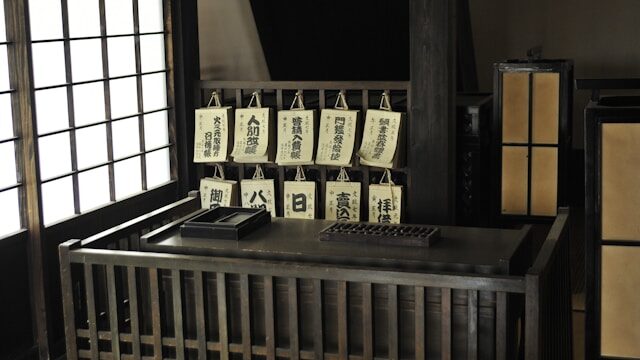「原子爆弾」その原理と製造~投下まで

私がこの本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、原子爆弾(今でいう核兵器)の仕組みについて知りたかったからだ。第二次世界大戦時、どのような思想、どのような状況下で原子爆弾を作ろうと思ったのか。どのような原理を利用したのか。とても興味があった。
原子爆弾 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで(山田 克哉、2025年7月、ブルーバックス)
原子爆弾の仕組み
結論から言うと、原子爆弾とは原子核の「核分裂」の仕組みを利用している。原子とは私たちの身の回りにある物質の最小単位となる小さな粒である。学問的には、物理学の範疇となる。
原理は単純
原子爆弾の原理は非常に単純である。原子核の核分裂の際に発生するエネルギーを利用するのである。原子核が核分裂を起こすと、凄まじいエネルギーが放出される。それをいくつも同時に発生させる。原理的にはそれだけである。しかし、この仕組みを人為的に達成するためには、多くの難題が立ちふさがったのである。
もっとシンプルに言うと、氷の塊に鉄砲玉をぶつけて割れば、氷が割れた瞬間に膨大なエネルギーが放出されることが分かった。これを集約して「瞬時に・同時に」発生させるのが原子爆弾である。氷を割ればいい、ということは分かった。後はどうやって効率よく、より多くの氷を割るかが問題であった。
戦争利用か平和利用か
核分裂のエネルギーを兵器利用したのが、原子爆弾(核兵器)。平和利用したのが、原子力発電である。よく、「原子力=悪」ととらえる人がいるが、技術というものは、それ自体は善でも悪でもない。それを使う人間側の問題である。刃物と同じだ。包丁が危ないといって取り除けば、我々は食事を食べられない。
登場人物の説明
「原子爆弾の原理=原子の核分裂」を語るうえでの登場人物を紹介する。この登場人物の役割と立ち位置を理解していないと、原子爆弾の仕組みについては理解できない。といっても、①原子、②原子核、③中性子の3つだけである。本当は、ここに電子や陽子なども登場しているのだが、今回は脇役なのであえて説明を省く。
【登場人物】
①原子:この世の物質を構成する最小単位。小さくて丸い粒。
原子の中には、原子核が入っている。
イメージ:梅干し
②原子核:原子の中心にある核。中には、陽子と中性子が入っている。
イメージ:梅干しのタネ
③中性子:原子核の中にある粒
イメージ:梅干しのタネの中の成分の1つ
原子爆弾を語るうえでの主役は、②原子核と③中性子となる。原理としては、梅干しのタネを割る時に、膨大なエネルギーが放出される。それを爆弾に利用するのである。
核分裂の発見 すべての始まり
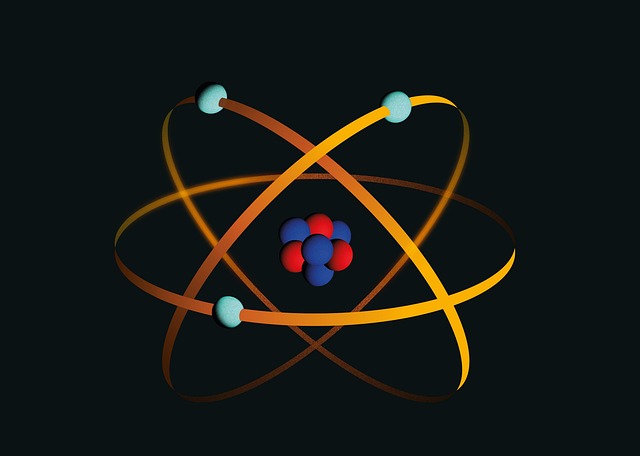
すべての始まりは、1938年に核分裂が発見されたことによる。ここでいう核とは、②原子核のことである。当時は原子核が分裂するなど科学者ですら夢にも思わなかった。しかし、③中性子を②原子核にぶつけると、原子核が分裂(壊れて二つに割れること)することが発見されたのである。この時用いられた原子が、後に原子爆弾の材料となる「ウラン」である。
凄まじいエネルギー放出
原子核の分裂自体も当時は凄い発見だったのだが、さらに驚くべきことは、この分裂時に凄まじいエネルギーが放出されるということが分かったのである。どれぐらいかというと、今までのエネルギー量の相場が5円ぐらいだったところが、2億円のエネルギー量が得られることが分かったのである。5円と2億円の差である。誰もが目を疑った。
※わかりやすいように単位を円に換えている
1kgのウランを分裂させると
たった1個のウラン原子を核分裂させると、2億ものエネルギーが得られることが分かったのである。このウランを1kg集めるとウラン原子の数は1兆個×1兆個となる。この1兆個×1兆個からそれぞれ、2億ものエネルギーが放出されるのである。得られるエネルギーの総量は、1兆×1兆×2億である。想像できないほどの数字ということが分かるだろう。
誰でも気がつく
核分裂が発見された翌年の1939年には、奇しくもナチスドイツがポーランドに侵攻して、第二次世界大戦が勃発する。そのような世界状況のなか、
・1個の原子核が核分裂を起こすだけで2億ものエネルギーが得られること
・どうすれば人為的に核分裂を起こすことができるか
このことは当時、論文として発表され「世界中」の科学者が知ることが出来た。
地球上の誰かがふと思った、「この原理を兵器に応用できないだろうか・・・」
原子爆弾という発想が生まれた瞬間である。この「誰か」の1人が映画にもなった、オッペンハイマーである。そして、実際に6年後の1945年に原爆投下までこぎつけるのである。
アインシュタインは関与していない
かの有名な、アルベルト・アインシュタインであるが、彼は原爆製造には一切関与していない。私は、関与していると思っていのだが誤りだったようだ。だが、製造には関与していないが、製造の後押しはしている。どういうことかというと、アメリカ大統領に原子爆弾の危険性やドイツが原子爆弾を開発する可能性を手紙で示唆したのである。もっともこれは、自主的ではなく、原爆推奨派の友人からの頼みに答えたのであった。
アインシュタインほどの人物なら、アメリカから「原爆製造スタッフに加わって欲しい」とオファーが来てもよいものだが、アインシュタイン自身が、平和主義者であったこと、軍事等の世界情勢に興味が無かったこと、機密保持の点で問題があったことなどから、アメリカは彼を「マンハッタン計画」のメンバーに加えなかった。
ドイツの科学力は世界一ィィィ~
当時、ヒトラー率いるナチスドイツが危険ということは認識されていた。それに加え、ドイツは科学力に優れており、多くの物理学者(特にユダヤ人物理学者)には、「ドイツが原子爆弾を製造したら大変なことになる」という恐怖があった。そのため、アメリカに亡命した多くのユダヤ人科学者が、アメリカに原爆製造を勧めるようになったのである。
世界の原爆取組み状況
しかし実際に蓋を開けてみると、世界情勢はこんな感じだった。
・ドイツ(ジャイアン):自分が強いので、切り札(原爆)に興味なし
・日本(スネ夫):ジャイアンと同盟を組んでいたので、そこまで必死さが無い。しかし、当時日本も原爆製造に乗り出していたことは事実である。
・アメリカ(のび太):ジャイアン怖さに死に物狂いでドラえもん(原爆)を製造し、奇跡的に成功させる。
アメリカの資源力が原爆を可能とした
結果として、アメリカという大国の予算、物量、科学者の数、施設の整備状況など、すべての条件が揃っていたので開発が可能だったのだと思う。日本の資源力では到底無理だった。ドイツも同じではないかと思う。こうして、アメリカで原子爆弾の開発が進められていくのである。しかし、それとて雲をつかむような難題の山積であった。
原爆製造の壁
当時の知識、科学技術力で原爆製造において困難だった内容は次の通り
①ウランの濃縮の問題
②連鎖反応の維持の問題
③起爆方法の問題
①ウランの濃縮問題
原子爆弾は、原子核の核分裂のエネルギーを利用するが、では「どんな原子でもいいのか?」というとそうでもない。核分裂を起こしやすい(壊れやすい)原子と、起こしにくい(壊れにくい)原子がある。当然、壊れやすい原子の方が原子爆弾の材料には向いている。
材料は「ウラン」に決定
原子爆弾の材料には、核分裂発見の元となった「ウラン」を使うことになった。しかし、このウランは致命的な欠点を持っていた。ウランは天然に存在する原子であるが、ウランの中にも「核分裂を起こしやすいウラン」と「核分裂を起こしにくいウラン」が存在するのである。しかも、その存在比率は、0.7:99.3である!
大部分のウランは役立たず
つまり、存在するほとんどのウランは「核分裂を起こしにくいゴミ」なのである。原子爆弾の原料となるウラン塊を1kg集めてもその中のたった、0.7%(7g)しか、材料として使えないということである。では、逆算して143kgのウラン塊を集めたら、そのうちの1kg(0.7%)で爆弾が作れるかというとそうでもない。不純物が多すぎて、爆発しないのである。
ではどうするか?材料となる希少な方のウランをチマチマ集める(濃縮)する必要があったのである。この濃縮技術の開発に膨大な時間と費用と施設を擁することになる。
プルトニウムの誕生
「当初」原子爆弾の材料は、ウランが選ばれた。だがその後で「プルトニウム」も原子爆弾の材料となり得ることが分かり採用されている。広島にはウランを使用した原子爆弾、長崎にはプルトニウムを使用した原子爆弾が用いられている。
プルトニウムは、1941年にウランを人工的に改造して作り出した元素である。映画、「バックトゥザフューチャー」で、タイムトラベルに必要な膨大なエネルギーを得るための原料が「プルトニウム」である。
②連鎖反応の維持問題
材料選定の次に難しかったのが、連鎖反応の達成である。確かに1個の原子を核分裂させると2億ものエネルギーが得られる。しかし、それだけでは兵器としては役に立たない。1兆×1兆個の原子核を瞬時に分裂させる必要があるのである。この「瞬時」の達成が難しかった。
ドミノ倒しの要領
連鎖反応とは、文字通り連続して継続的に(連鎖的に)反応が進むことである。最初は1つの核分裂から始まり、そこから玉突き的に次々と分裂が発生しなければならない。しかし、材料の量が少なかったり、不純物が混じっていたりすると途中で連鎖反応が止まってしまう。こうなると途中で中途半端に爆発するショボイ威力の爆弾になってしまう。
途中で止めてはいけないドミノ
いうなれば、膨大なドミノ崩しを途中で止まることなく最後まで成功させなければならないのである。そのためには、倒れやすいようドミノをどのように並べればいいのか等の工夫が必要となる。
③起爆方法の問題
兵器として使用するからには、①人為的に②任意のタイミングで爆発させる必要がある。ダイナマイトであれば、導火線がジジジと燃えていき、その間に避難してドカーンとなる。しかし、当時、これを原子爆弾に当てはめることは難しい問題であった。
臨界量の算定
臨界量とは、連鎖反応を起こすために(原子爆弾としての威力を発揮するために)「最低限必要な材料の量」である。ウランでは1kgとなる。核分裂(原子爆弾)の起爆剤は、中性子である。しかし、この中性子という物質は、我々が気づかないだけで日常的に宇宙から降り注いでいるのである。
勝手に爆発問題
ここに臨界量である1kgの濃縮ウランを用意する。この臨界量のウランは、人間が何もしなくても宇宙から飛来した中性子を起爆剤として、いきなりドカンということがあり得るのだ。自然爆発する原子爆弾など危なすぎてとても扱えないし、兵器とは言えない。このようなことから、起爆の問題が持ち上がった。
分けたものを合体(ガンバレル型)
当時の科学者はどうしたか?ウランの1kgの塊を2つに分け(それぞれを1kg以下にして)、人為的に合体させ1kgにして爆発させる、という方法を編み出したのである。この方法は、一方の塊をもう一方の塊に向けて発射してぶつけるので、ガンバレル型と呼ばれている。広島型原爆には、このガンバレル型が使用された。
潰して圧縮(インプロ―ジョン型)
ガンバレル型は、ウランには使用できるが、プルトニウムには使用できないことが分かった。プルトニウムは、ウランよりさらに不安定な物質であり、自発的に核分裂を起こす可能性が非常に高かったからである。そこで、別の方法を考える必要があった。
外側から圧縮
思いついたのが、プルトニウムを球体の器に入れておき、これを外側から爆発させその圧力で内側に圧縮する方法である。するとプルトニウムの密度が高まり一気に臨界量以上に達して、核分裂反応が起こるのである。現在の核兵器もほとんどがこの爆縮(インプロ―ジョン)方式を採用している。
「マンハッタン計画」の始動

1942年(昭和17年)6月17日 、ルーズベルト大統領は、原子爆弾の製造を正式に認可した。「マンハッタン計画」の始動である。1938年の核分裂発見から、たった4年で軍事利用となっている。この頃の日本は、太平洋戦争のターニングポイントであるミッドウェー海戦で敗北していた。
連鎖反応の実現に成功
1942年12月、アメリカは世界で初めて人為的な核分裂連鎖反応を成功させる。人類が、途方もない原子力エネルギーをコントロールすることが出来るようになった瞬間である。これで、②連鎖反応の維持問題が解決された。
1945年春 濃縮問題解決
この頃になり、アメリカはようやく原子爆弾に必要とされる量のウランとプルトニウムを製造できるようになっている。このためにアメリカは、プルトニウム製造のための原子炉やウラン濃縮のための施設、はたまたこれら施設のための発電所まで建造しているのである。まさに、国家の威信をかけての一大事業である。これにより、①ウランの濃縮問題が解決しつつあった。
こんな途方もないことが出来たのは、やはりアメリカの物量しかなかったであろう。ちなみに、アメリカが原爆製造に使った予算は当時で20億ドル。日本の原爆開発予算は2万円であった。。。まったく、お話にならないレベルである。こんな国を相手に戦争して本気で勝てると思っていた当時の日本軍人の頭の中がお花畑過ぎる。
1945年7月 トリニティ実験
1945年(昭和20年)7月16日、アメリカ、ニューメキシコ州において世界初の核実験「トリニティ実験」が行われ成功している。これで、③起爆の問題も解決された。日付に注目してもらいたい、1945年7月16日である!終戦の僅か1ヶ月前である。
この頃のアメリカは、まだ原爆を実戦投入できる状況ではなかったのである。最初にポツダム宣言が日本に対して行われたのが7月26日。もしこの時、素直に受託していれば日本に原爆が落ちることは無かったのである。(落としたくても落とせなかった)
助かったドイツと落とされた日本
ドイツは、1945年(昭和20年)5月に無条件降伏している。そのため、原爆の被害を免れている。さっさと降伏して助かったドイツ。負け確定にも関わらず、意味不明の根性論で粘って原爆を落とされた日本。皮肉なものである。本当に今の北朝鮮とかを笑えない。
日本への原爆投下
ポツダム宣言を無視したことで、アメリカは原子爆弾を日本に投下することを決定する。ぶっちゃけ、日本の黙殺は織り込み済みであり、アメリカとしては原爆投下の大義名分を得たことになる。
当初の攻撃目標
当初原爆の投下候補都市は、京都、広島、新潟、横浜、小倉、長崎となっていた。しかし、アメリカの理解ある人物が、「京都には歴史的文化遺産が多数あるので、攻撃目標から除外すべし」と助言し、京都は対象から外れることになる。この助言がなければ、京都御所、清水寺、二条城などは現存していなかっただろう。最終的には、広島、新潟、小倉、長崎の4都市へ絞られた。
小倉から長崎へ変更
2発目の原子爆弾は、当初小倉に投下される予定だった。しかし、当日(1945年8月9日)の小倉が土砂降りの雨で視界ゼロであったため、急遽長崎に変更され投下された。先延ばししてやり直す、という選択肢はアメリカにはなかったのであろう。
まとめ
原子爆弾の着想~開発、原爆投下までの経緯は以上である。当時、原爆の着想はどの国でも持っていたので、アメリカだけが特別というわけではない。日本ですら製造を考えていたぐらいである。
しかし、巨額の予算を投じたアメリカが、「意地でも」原子爆弾を使って実績を残したかったことがうかがえる。決して、戦争の早期終結のためなどではないことは確かだ。本当にそうであれば、最悪でも広島への1発だけで充分であった。長崎への投下など、当初は8月11日の投下予定を2日繰り上げしているぐらいである。
エピローグ
核兵器の存在しない世界線
本書でも触れられているが、「核分裂の発見が、第二次世界大戦の後であれば原子爆弾は製造されなかった可能性が高い」核兵器の無い世界線が存在したかもしれない。戦時下という特殊な状況が、なりふり構わず核のエネルギーを兵器利用したのである。
クローン兵器の可能性
クローン技術。平和な現在は、倫理的な問題からクローン人間の開発は抑制されている。しかし、戦争のタイミングによっては、原子爆弾同様クローン兵器も誕生していた可能性は大いにある。
人的な兵力不足に悩む国家が開発に踏み切ってもおかしくはない。また、細胞から造られたクローン人間には、死んでも悲しむ家族がいないので世論の了解も得やすいだろう。おそらく、現在の技術的にクローン兵士の製作は可能だと思う。成長スピードの課題はあるが、原爆開発同様、戦争という特殊状況がそういったものを乗り越えさせるのだろう。
使えるモノはなんでも使う
実際にドローンについては、ウクライナの戦争で既に軍事利用されている。戦時下においては、利用できるものは何でも利用するのは世の常である。肝心なのは戦争をしないことであるが、人間はおろかなので過ちを繰り返すのだろう。