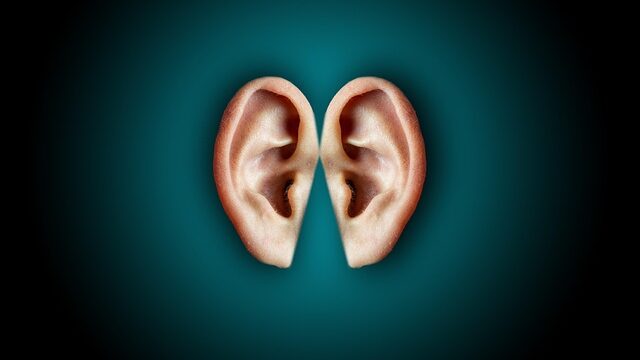「新・空き家問題」あなたの実家、大丈夫ですか?私は大丈夫じゃない。。。

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、将来この本に書かれているような空き家を、私自身が処理する立場になる可能性が高いからだ。早ければ5年以内に訪れるだろう。そのために、今から予備知識を得ておくことを目的としている。
この本をお薦めする人
もしあなたが、実家の処分に頭を悩ませているのであれば、本書は役に立つだろう。特に事前対策が重要であるため、親が元気なうちにある程度の方針を立てることもできる。親が認知症になってからでは遅いことも多々あるからだ。
他にもおひとり様(独身者)の家の処分の方法も書かれているので、あなたが独身者で持ち家があるのなら、自分の亡き後どうするかの参考になるかもしれない。借家に関しては何も書かれていないので、賃貸住まいの人には縁のない本である。
新・空き家の問題(牧野知弘、2025年2月、祥伝社)
私が処理すべき空き家の候補
私が近い将来、処理すべき空き家の候補は2つある。それらの処理の事を考えると今から憂鬱である。それは次の2つの家である。
①私の独身叔母の家
昔は私の母方の祖父母が住んでおり、今は生涯独身の私の叔母が住んでいる。この叔母が亡くなった後に、誰かがこの家を処分しなければならない。立地はそれほど悪くないが、いかんせん築年数が古い。致命的なのが、長屋形式で単独で解体もできないし建て替えも出来ない。現状のまま処分しなければならない。
②妻の実家
妻の実家も悩みのタネである。こちらは、かなりの田舎にありおそらく誰も引き取り手が無いだろう。戸建て住宅であるが、少し前までは借地なのが救いであったが、義父が勝手に土地を購入したらしい、、、というか貸主(前所有者)から買わないかと持ち掛けられて買ったようだ。完全にババを引かされている。事前に相談があれば、絶対に辞めさせたのだが残念ながら事後報告であった。
唯一の救いは、現在私の親が住んでいる実家は、弟が相続することに決まっていることだ。
増え続ける日本の空き家
前振りが長くなったが、本書ではこのような処分困難な空き家の現状について書かれている。2023年現在の日本の空き家は全国で約900万戸とある。実に7戸に1戸が空き家という衝撃の事実である。にもかかわらず、都内のマンションは争奪戦で平均相場が1億とかいう状況だ。何かがおかしい。
約半数が個人所有空き家
空き家と、ひとくちに言ってもその形態は様々である。日本の空き家を代表するのは、①賃貸住宅の空き家と、②個人が所有する空き家である。このうち、①が約44万戸で空き家総数の約50%を占める。②が約43万戸で、空き家総数の43%を占めている。①については、いずれ借り手が付けば空き家で無くなる可能性が高いが、②は将来の見通しが暗い。
個人所有空き家ワースト県
参考までに個人所有の空き家数が多い都道府県を挙げていくと、1位:大阪府(約230万戸)、2位:東京都(約210万戸)、その後、兵庫、北海道、千葉と続く。空き家というと田舎の朽ち果てた家というイメージがあるが、日本の人口が集中している地域で空き家数が多い。これは単純に住戸の母数が多いことが理由として考えられる。
空き家を所有するに至った理由
どうして個人が空き家を所有することになったのか?まぁ、考えなくてもその理由はおおよそ想像がつくと思うが、理由の圧倒的1位が「相続」である。家なんて簡単に手に入るものでもなし、一般庶民が自宅以外に家を所有する理由は親から相続する以外にないだろう。
郊外と田舎が空き家天国
本書で紹介されている空き家には特徴がある。ひとつは「都心部の郊外の空き家」これは、高度経済成長期以降に、自分たちの親が購入した自宅である。かつては自分たちが住んでいた、沿線の家である。しかし、都心回帰の人気により独立した子供(我々世代)は、別途家を所有しており、今更郊外の親の家は必要ない。これらが空き家化する。
もうひとつが、自部たちの親の親、つまり我々の祖父母がかつて住んでいた「田舎の空き家」である。これは自分たちの親が既に相続しており、おそらく放置されている空き家を子供である我々が再度相続するパターンである。(本書では2次相続と書かれている)
親が処分しきれなかった祖父母の家を孫に引き継がされるのである。私の場合も、義父の田舎の実家を引き継げば、最悪自分たちの子どもに相続させることになりかねない。
空き家問題を解決する方法
本書では空き家問題を解決する方法は”5つ“しかない”と書かれているので、それらを紹介する。最初の大きな分岐点は、家を「残す」のか「残さない」のかである。
家を残す場合の解決策
家を残すと決めた場合の解決策は3つある。
①当面空き家として残しておく
②有効利用する
③賃貸または売却
①については、そのまま放置につながるので実質解決策と言えるかは疑問である。しかし、多くの空き家は①の措置を取っていると思われる。(だから空き家になる)②については、子供の誰かが住むぐらいしか思いつかない。個人的には③の「売却」が最善の手段だと思っている。たとえタダ同然だとしても。
家を残さない場合の解決策
家を残さない場合の解決策は、2つある。
④更地にして活用する
⑤更地にして借地または、売却
④は青空駐車場での利活用だろうか。やはり個人的には、都心部などのよほどの一等地でない限り、安くてもいいのでさっさと売却して手放したいという気持ちが強い。
私が空き家を手放したいと思う理由
私が空き家を相続せざるを得ない状況になった場合は、すぐさま売却するという選択肢を選ぶだろう。理由は、これからもっと空き家も増えてきて引き取り手がいないことと、不要な土地建物を所有しているだけで維持費(税金や修繕費)が必要になるからだ。収益を生み出さない、空き家のランニングコストもバカにならない。
家が安く買える時代の到来
これまで「所有する側」のデメリットを書いてきたが、空き家問題で唯一のメリットとなるのが「買い手側」の事情である。空き家が増えれば増えるほど、安く買える可能性が高くなるということだ。
本書では、首都圏の実例が示されているが東京でも多くの家が「余っている」状況である。今後15年間で首都圏で少なくとも370万戸の相続が発生するとのこと。年平均25万戸の空き家が“発生し続ける”のである。
新築8万戸に対して25万戸の空き家?
現在の首都圏での新築供給、中古の住宅の売買の総数は約8万戸とある。つまり、誰かが家を買っている(需要)の件数が8万戸ということである。これに対して、相続が毎年25万戸発生(供給)するとか、もう無茶苦茶である。
低く見積もって相続物件の1/3が売却されたとしても8.3万戸となり、毎年の需要8万戸に匹敵する供給量である。日本は新築志向が非常に高いが考え方を変えれば、中古であれば家が安く買える時代。もしくは、安い賃貸で何とかなる時代が来る可能性が高い。
家への価値観が大きく変わるかも
かつて専業主婦が当たり前であったが、令和の時代は夫婦共働きが当たり前である。同じことが家の問題でも起きるかもしれない。かつては35年もの長期ローンを組んで家を“所有”するのが当たり前であったが、令和20年頃は余りまくっている家を賃貸するのが主流になり、家を買うという考え方は無くなっているかもしれない。
まとめ
今からの時代を生きる人にとっては、空き家は天の助けかもしれないが、実際に今所有する側にとっては頭の痛い問題である。特に妻の実家はそこに行くだけでも1日仕事になりそうなので、できれば関わりたくないのだが・・・義父よ、なんで黙って土地を買ったのか、本当にやめて欲しかった。