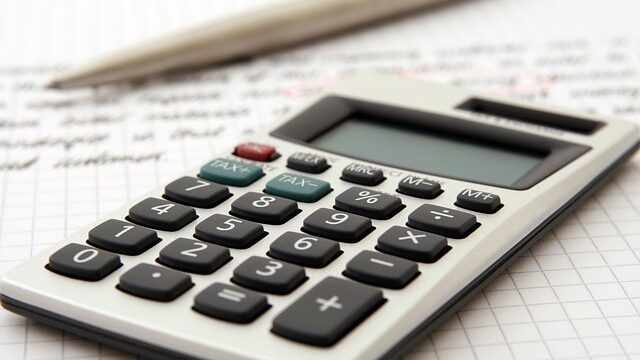【危険物乙4】”一発合格” 勉強方法や取得費用まとめ

受験資格が無いため、資格取得特集などで紹介されることの多い国家資格、「危険物取扱者乙種第4類」。通称、乙4の試験を受けてみた。結果は、”一発合格”できたので、取得までの内容をまとめてみる。
危険物乙4試験の概要
試験概要
・危険物第4類(ガソリンや灯油、軽油等の引火性液体)を取扱うための資格
・受験資格なし
・試験は各都道府県で受験可能
・受験料:5,300円(2025年1月現在)
どこの都道府県でも、概ね年間4回は開催されている。東京では毎週のように開催されているようだ。自分の居住地以外の他府県でも受験可能、かつ他府県との受験日は被っていないことが多いので、実際にはもっと数多く受けられると思う。
試験科目
試験は下記の3分野から出題され、「すべての分野で6割以上得点」する必要がある。ひとつでも未達の分野があれば、他が満点でも足切り不合格となる。
・危険物に関する法令:15問出題9問以上
・物理・化学:10問出題6問以上
・危険物の性質と消火:10問出題6問以上
合格率
乙4の合格率は3割~4割と言われている。これは受験者のすそ野が広いため、あまり勉強もせずに取りあえず受ける、という人が多いので合格率の低下につながっていると思われる。
詳細については試験を開催している「一般財団法人 消防試験研究センター」を確認してもらいたい。
勉強方法等について
ここからは私が実際に行った試験勉強について書いてみる。
勉強期間は独学で約1.5ヶ月
勉強期間は1.5ヶ月ほど、それでも余った感じである。がんばれば1ヶ月でも間に合うのではないか。勉強方法は独学である。独学でもまったく問題ないと思う。勉強時間は、毎日自宅で30分程度、参考書を読んでいた。通勤等での勉強は行わなかった。
参考書は1冊
使った参考書は、公論出版の「乙種4類 危険物取扱者試験 令和7年版」税込み1,870円。これ一冊だけである。この本のいいところは、解説よりも問題掲載を重視している所。ひたすら過去問をやって覚える、ということを繰り返した。1.5ヶ月で2~3周は繰り返すことができる。
補足として、参考書の隅から隅まで覚えたわけでは無い。使った参考書には、「試験に特に出題される分野」について☆マークがついていたので、その部分のみを勉強した。なので、まったく勉強しなかった分野も結構あった。
試験結果(得点率)
私の試験結果(得点率)は以下であった。(6割以上で合格)
・危険物に関する法令:13/15(86%)
・物理・化学:10/10(100%)
・危険物の性質と消火:9/10(90%)
問題の内容は、素直な問いが多い。落としてやろう、という意地の悪いひっかけ問題はなかった。参考書に掲載されていた過去問の類似問題も出題されたし、初見の問題もあった。初見でも、感覚的に解ける問題であった。
極限までシステム化されている試験
この試験は、大学の入学試験や司法試験、その他難関国家資格のような年に1回だけという試験と異なり、開催回数が非常に多い。そのため主催者の負担を減らすためだろう、試験自体が可能な限りシステム化されている。
申し込みから受験料の振り込みまで、基本はネット。受験票ですら、自分でプリントアウトして持ってこいという状況である。私は自宅にプリンターがないので、会社でこっそり出力した。
受験生対策はバッチリ
プリントアウトした受験票に、顔写真を貼って試験当日に持参するのだが、顔写真を忘れてくる人もいるようだ。しかし、侮るなかれ主催者側もそういう人達の行動すらも既に対策済である。相手も伊逹に場数を踏んでいるわけではないようだ。
試験会場に写真撮影場所があったり、写真を張り付けるためのハサミやノリ、マークシートへの書き込み用えんぴつの貸し出しも行われている。どんだけ、至れり尽くせりの試験なのかと思った。しかし主催者側からすれば、試験直前にこのような忘れ物系の受験生の扱いに手間取って、試験開始が遅れる方が困るのだろう。
本当に手厚い待遇でビックリした。普通の試験であれば、当然忘れた受験生が悪いので門前払い、「来年また来てくださいね」であろう。
極めつけが、試験の帰りに「合格した時用」の免状申し込み書類を配布していることだ。合格者に再度イチイチ書類を発送したり、問い合わせに応じるよりは、ここで全員に配っておいた方が効率がイイという考えなのだろう。
合格発表とその後、費用合計
私の場合は、受験から約3週間後に合格発表があった。正午に試験センターのHPに掲載される。翌日にはハガキで通知が届いていた。このハガキは、後々免状の申し込みに必要となる。ここで試験の帰りに配布された、申し込み書類が威力を発揮する。すぐに申し込みが出来るのだ。免状交付手数料として2,900円必要となる。
かかった費用合計
免状取得にかかった費用は、約1.1万円である。その内訳をまとめてみると、
・受験料:5,300円
・顔写真:1,000円
・参考書:1,870円
・免状交付手数料:2,900円
合計すると約1.1万円となる。その他、試験地までの交通費は別途となる。
使うアテはあるのか?
資格を取得して使うアテがあるのか?と聞かれると、今のところまったくそんな予定はない。しかし、一度取得すれば生涯有効なので、いつか(例えば定年後)ひょんなことから役に立つ時が来るかもしれないと思い、まだ頭が回る今のうちに取得した。
それとガソリンや灯油など、身近に扱う危険物の特性や消火方法について知識を得られたのは良かったと思う。