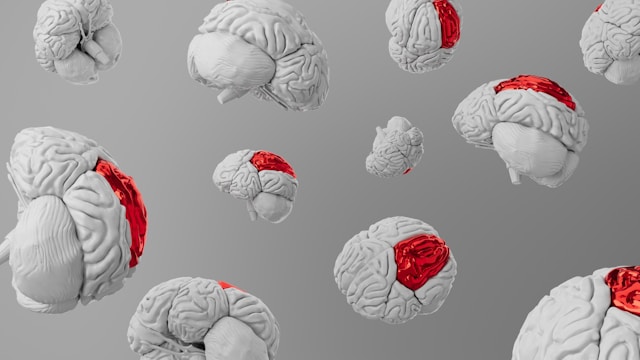【読書】「論理的思考とは何か」答え:万国共通の思考法など無い

この本を読もうと思った理由
書店でパラパラとめくった時に、日本の文章は「今日は朝起きて〇〇して、□□だった。」という内容に対して、アメリカは「今日は□□だった。その理由として、朝起きて〇〇」という例が示されており、日本は感想文方式、アメリカは結論が先と書かれていた。この違いはどこから来るのかと、非常に興味を持ったのが1つ目の理由。
普段仕事で議事録や報告書を書くので、色々な文章の書き方を知っておけば業務に役立つのではないか、と思ったのが2つ目の理由。論理的思考というより、論理的な文章の書き方を学びたいと思った。
論理的思考とは何か(渡邊雅子、2024年10月、岩波新書)
本書のまとめ
本書の内容をまとめると以下の様になる。
・世界には4つの作文の型(論理的思考の型)がある。アメリカ式、フランス式、イラン式、日本式となる。
・ゆえに、万国共通の普遍的な論理的思考法というものは、「存在しない」
・何を「論理的」と評価するかは、4つの型(文化圏)によって異なる。
・論理的と評価されるためには、書き手と読み手(評価者)の価値観(論理の型=文化圏)が一致する必要がある
・日本式論文をアメリカ人に評価させても落第となるのは、この不一致によるもの。逆も然りだし、他の組み合わせも同じ
・これからは、4つのうち“どの型”の思考法が求められているのかを推察し、「使い分ける」必要がある
ひらたく言うと、母国の味付けは他国ではおいしいと評価されない、ということ。同郷の者にしか分からないということである。
4つの思考法
序章の段階で4つの思考法が紹介されていた。正直この考え方を知れただけでも面白かった。
①論理学
既知の事実から他の真偽を考える
演繹(えんえき)的な考え方。というかこの言葉自体初めて知った。既知の正しい大前提から、個別の内容を判断する方法。具体例として、①人間はみな死ぬ、②私は人間である、③ゆえに(人間である)私は必ず死ぬ、という考え方。正しいか、正しくないか、がすべてであり、そこが次のレトリック(説得)と大きく違う点。
②レトリック(説得)
説得できれば内容の正確性は二の次でいい
日常的にこの思考法が最も身近であろう。この場合、「蓋然的(がいぜんてき)推論」=100%正しくはないが概ね正しい、という考え方が用いられる。要は相手を説得できれば、100%正しくなくとも良い、ということである。
よって発言内容の正しさの他に、①誰が述べているのか(あのインフルエンサーが言うのなら間違いないだろう)や②感情論(若者は搾取されている、だから立ち上がるべきだ)なども加味されるとある。特に感情に訴えかけるのは、理屈(正しさ)よりも効果的とある。逆に発言者の信用が低ければ、言っていることは正しくとも信用されない場合もある。
③アブダクション(科学)
既知の結果から仮説を立て原因を探る
アブダクション(遡及的推論)とは、“ある結果”から原因を推論すること。常に結果が既知であり、そこから仮説を立てて実験や検証により、未知の原因を究明するという、いかにも科学的思考法である。具体例として海王星の発見が挙げられていたので紹介する。
海王星が発見される以前の話、
①天王星の軌道は、理屈では説明できない動きをしている。(既知の結果)なぜだ?
②天王星の軌道に影響を与えている、未知の天体が存在するのではないか?(結果に基づく原因の仮定)
③②の仮説が正しいと“するならば、”未知の天体”は、計算上この辺りに存在するはずだ。
④③に基づいたポイントを観測した結果、海王星が発見される。
⑤やはり、我々の立てた仮説は正しかった。
漫画デスノートでニアが「捜査というものは(こいつを犯人と仮定して)決めつけてかかり、間違っていたらごめんなさいでよい」というセリフを思い出した。
④哲学
「〇〇とはなに?」の物事の本質に迫る。
哲学の目的は、「物事の本質」をとらえることとある。具体的には、「美とは何か?」という問いに対して、「美とは〇〇である」というような、これまたいかにも哲学的イメージそのままの思考法である。
ここでいう「物事の本質」とは、(例えば)美とは、モナ・リザという“具体的な物質”ではなく、抽象的な概念について定義することとある。このため、幸福や正義などといった、「立場によって答えが変化する内容」が哲学の議論の対象になる。そして哲学の目指すところは、100%の定義づけではなく「可能な限り両者の共通の了解」に達する、というのがおもしろい。
4つの作文の型(論理的思考の型)
本書のメインとなるのが、これから紹介する4つの作文の型である。
①アメリカ型エッセイ
アメリカ型のエッセイは、「効率的か否か」を重視した直球勝負である。最初に結論を述べて、次にその根拠を述べる。最後にもう一度まとめる。「私は〇〇と考える。なぜなら・・・」形式となる。
利点として、書き手が何を言いたいのかすぐに理解できるところ。欠点として、自分の主張が正しいかどうかの客観的考察がなされないこと。この欠点により、しばしば間違った結論付をやってしまう。また、最初に結論を述べるのは、このアメリカ型のみとなる。他の3つは結論が最後。
現在は世界がアメリカ中心的なこともあり、結論が最初にありきのエッセイ方式は、ビジネス等では世界標準形式になりつつある。結論を先に述べる方式は、我々日本人でもある程度なじみはあるだろう。
②フランス型ディセルタシオン
フランス型のディセルタシオンは、「十分な審議が行われたかどうか」に重きを置き「弁証法」を基本構造とする。論文の形式は<正―否―合>という流れとなる。論文の主題に対する一般的な正しい見解を述べ、次に筆者自身がそれを否定する立場で話を進める。最後に両者の融合的内容を<合>でまとめるとある。正と否が存在することで審議となる。
特徴的なのは、<正―否―合>という型どおりに書けたかどうか、が評価の対象らしい。どんなに素晴らしい内容でも、型どおりでなければ不合格となる。また、根拠となる資料はすべて、古今の著名な思想家や作家の作品からの「引用」しか認められない。日本であれば出生統計などのデータを根拠として用いるが、そういうのは認められない。
③イラン型エンシャー
イラン型のエンシャーは「真理か否か」が重要な観点となる。最大の特徴は論文の答えが「すでに外部から与えられている」という点である。外部とは、神や宗教的観念の真理である。よって、書き手の個人的見解や独創性は期待されておらず、書くことは「許されていない」。理由は神が決めたものに対して、一個人が意見などして良い訳が無い、とう考えである。
④日本型感想文
日本型の感想文は、「共感されるか否か」を重視する。感想文とは「生活の中での直接の体験や見分について、自分の思ったことを書き表した文章」と定義される。100%主観となるので、③のイラン型とは真逆の発想となる。
このような感想文は小学校の読書感想文に始まり、私が今まさに書いているのも読書感想文である。他にも各レビューなどが、そうではないだろうか。感想文には、①自己の体験を通じて、②その経験を今後の生活にどう活かしていくのか、そういったものが求められる。そして感想文をまとめる型として、日本人なら誰でも知っている<起承転結>が登場する。
4つの型についての説明は、これで終わる。本書では、それぞれの立場から見た他者をどう評価するか等の内容も示されているので、興味のある人は実際に読んでみてもらいたい。
まとめ
このように4つの型、それぞれの考え方自体がまったく異なるので、他者(他の型の論理的思考)を理解することはできない、とまとめられている。これはある意味必然だと思う。世界で通じる絶対的な正解はない。価値観は地域により異なる。このような状況への対応策としては、その場で「求められている型」を選択すること、とあるが、そこまでグローバルな仕事をしていないので、私には必要なさそうだ。
慣れ親しんだ日本型感想文(笑)として私の意見をまとめると、アメリカ式の直球は理解できるが、フランス型とイラン型は、想像もつかない状況である。しかし、このような論理的思考の“型”が世界に存在する、とわかったので面白い本であった。
仕事に活かすのは厳しいか
私がこの本を読む動機となった、「仕事に活かせるかどうか」という問いには、「無理だろう」というのが結論である。せいぜい、アメリカ型で結論を先に書くことぐらいなら理解されるかもしれないが、やはり日本人には日本人向けの味付け(書き方)が、一番しっくりくるのだろう。
無理して他国の味付けにしても評価はされない。逆に考えれば、日本型論理的思考法を学べば仕事の役に立つということだ。今度は、そういった本を探してみたい。
仕事に活かしたいなら、こちらの本の方が役に立つかも。