【読書】「貧困と脳」因果関係を知りたかったのだが、少し違った
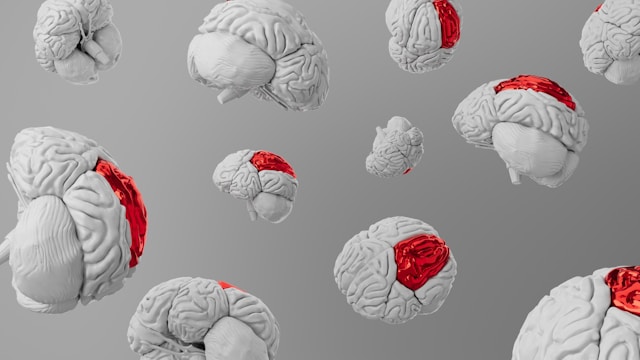
この本を読んだ理由
私がこの本を読んだ理由は、タイトルにある通り「貧困と脳」には、どのような因果関係があるのかを知りたかったから。そう思う動機には、次のようなものがある。
私が担当する外注先に、本当に仕事をサボる人がいる。具体的には提出期日を守らない、何度指示をしても行動しない。そういったものに対して、当然こちらのイライラは募る。「なんでそんなにいいかげん(ズボラ)なのか」社会人としてどうなのか。あなたのその遅れのせいで、こっちがどれだけ迷惑を受けているのか。結果的にその外注先は、ウチの会社からの仕事を失った。
書店でこの本を見た時に、「実はやらないのではなく、出来ないのではないか?」という疑問を感じたのが、本書を読んだ理由である。この本を読んでみて、本当に(脳の何かが理由で)仕事が出来ないのか、単にサボっているだけなのかを判断したいと思った。
貧困と脳(鈴木大介、2024年11月、幻冬舎新書)
私が期待していた内容ではなかった
結論として、残念ながら私が期待していたようなことは書かれていなかった。この本で紹介されている事例は、「疲れる脳」と表現され、もはやれっきとした「疾患レベル」の状態であり、仕事を継続できないのは当然で、だから貧困に陥るという状態の事例ばかりであった。
病気レベルにまで脳の認知機能が低下しているため、生活保護などの手続きも行えず、他人にも助けを求められず、より貧困になるというのが本書の内容である。
私が対峙していた人物は、この本で紹介されているような、書類作成すら出来ない状況や、記憶が瞬時に失われてしまうというようなことは無かったので、脳は正常の範囲と考えらえれる。私としては、「脳は健常な状態」にありつつ、強度のずぼらとの境界線や、思考との因果関係についての情報を知りたかった。
知識としては有効
健常者であっても突然そのような「働けなくなる脳」という状況に陥ることがある、ということを知ることができたので、この本を読んだ成果はあったと思う。残念ながら、どういう過程をたどれば、健常者がそのような状況に陥るのかという原因については、記されていなかった。本書は医学書ではないので、そこまでは望みすぎかもしれない。原因を知れば、そうならないための事前対策も行えると思ったのだが。
しかし、身近で同僚が突然様子がおかしくなった場合、このような事例を疑って救いの手を差し伸べることが出来るかもしれない。自分自身が陥った場合は、おそらく本書の内容を他人に伝えるほどの思考力は残っていないだろう。。。














