【読書】「学問のすすめ」学生向けに勉強しなさい、という内容ではない
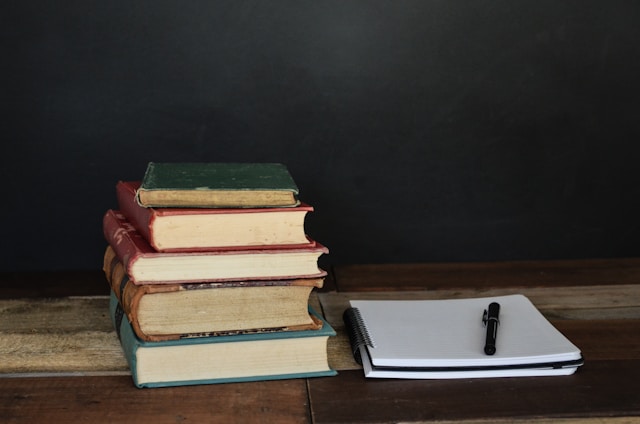
この本を読もうと思った理由
今は新札に変わってしまったが、1万円の代名詞である「諭吉」こと、福沢諭吉の書いた「学問のすすめ」を読んだ。この本を読もうと思った理由は、「まぁ、有名な著書だし一度読んでみるか」程度である。「学問のすすめ?昔読んだことはあるよ」と、誰かに言うためのアリバイ作りでもある。そして、ここにまとめているのは、読んだ内容を忘れないためである。まさに、ファスト教養的思考だ。
まとめ
結論としては、「学生に勉強しなさい」と説く本ではない。知識を習得し、国家のレベルを底上げしようという内容である。よりスムーズに内容を理解したかったので、ちくま新書の「現代語訳 学問のすすめ」を読んだ。
現代語訳 学問のすすめ(福沢諭吉、2009年、ちくま新書)
福沢諭吉について
福沢諭吉について私は、おなじみの一万円札の人と、慶応義塾大学を創設した人ぐらいしか知識が無い。生きた時代としては、天保5年~明治34年(1835年~1901年)66歳没となる。大政奉還が1867年なので、福沢32歳の時である。新一万円札の渋沢栄一(天保11年~昭和6年(1840年~1931年)91歳没)とは、生まれはほぼ同じだが、渋沢の方が30年長生きしている。
学問のすすめが発表されたのは、明治元年~7年(1868年~1874年)今から約150年前である。福沢が35歳前後の頃となる。時代背景としては、列強の西洋に立ち向かうべく、という時期となる。西洋の植民地となることなく、しっかりと日本の自治権を主張していこう、という意気込みを感じる。
よって小学校、中学校からしっかりと勉強しましょうね、というものでは無く、しっかりとした国を作るにはどうすればいいか、というような内容が多い。以下私が「学問のすすめ」を読んで、興味を引かれた点をまとめてみる。
初っ端から手厳しい
学問のすすめの出だしで有名な、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」だが、これは人は生まれながらにして平等、と説明されている。本書ではその直後に「しかし、」となり「世間を見わたすと、賢い人とバカな人、お金持ちも貧乏人もいる“雲泥の差だ”なぜか?」と続く。
そして、その原因は「ハッキリしている」とある。すなわち「人は学ばなければ愚か」、賢い人とバカな人の差は、”学ぶか学ばないか”である、と書かれている。非常に手厳しい。他にも「万物の霊長たる人間が、自分の衣食住だけで満足し社会的(国家への)貢献をなさないのは、“蟻”程度の(ゴミのような)存在である」と書いている。
怨望は諸悪の根源
本書で福沢諭吉は、「人間には色々な欠点があるが、その中で最悪なモノが“怨望(えんぼう)”である」と書いている。怨望とは、他人をねたむ心である。怨望の前では、欲張りやケチ、贅沢、誹謗などは、ものの数にも入らないとなっている。誹謗については少し疑問だが、福沢は誹謗か正当な意見かを判断する必要があると述べている。
【怨望の原因】
怨望(ねたみ)の一番よくない点は、他人に害をなすこととある。怨望の起こる原因として「窮」とされているが、これは貧困などの事ではないとされる。ここでいう「窮」とは、自由にふるまえない抑圧された状態となる。具体的には言論の自由が無い、行動の自由が無いといった状態である。
現代で言論の自由や行動の自由は保障されているが、とにかく怨望(ねたみ)の心は持たないように気を付けよう。
疑ったうえで判断せよ
「(簡単に)信じることには偽りが多く、疑うことには真理が多い」と書かれている。なかなかに深い言葉だ。西洋諸国が発展したのも、すべて疑うことが発端と書かれている。ガリレオの地動説、ニュートンの万有引力然りというわけだ。逆に「簡単に、楽して」などは、詐欺(偽り)が多いということだ。
【判断するためには学が必要】
物事の善悪は、自分で疑って判断しなければならない。そのためには、学が必要とある。確かに何かを判断するためには、多くの事例や多面的な見方が必要となる。そのための知識を学問から得よ、ということだろう。
仕事を辞める若者へ向けた言葉
こんな(くだらない)仕事は自分には向いていない。この会社のやり方は古すぎる。こんな風に他者の批判ばかりで、すぐに仕事を辞めてしまう若者は令和の時代にも多いが、明治の時代にも多かったようだ。そんな若者に福沢諭吉は、次のようなアドバイスをしている。
【いっぺん自分でやってみろ】
「他人の仕事を見て物足りない(要領が悪い)と思うなら、一度自分で引き受けてやってみろ」とある。自分でやってみて、もっと上手くできるならそれでよし。やってみると意外と難しく、自分が無知だったということを学ぶ機会になるかもしれない。ハタで見ているのと、実際にやってみるのとでは、全然違うということに気づくだろう。「言うは易く行うは難し」である。
まとめ
現代の感覚からすれば、国家への貢献など知ったことかと、感じる人も多いかもしれない。しかし、一度も他国の植民地にならず、日本という国が存在できたのも過去のこのような先人たちのおかげというのは、覚えておく必要があると思う。
私的には学生が読むよりも、社会人が読むべき本という感じを受ける。














