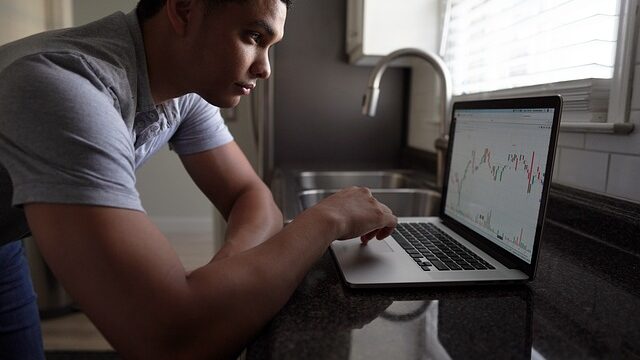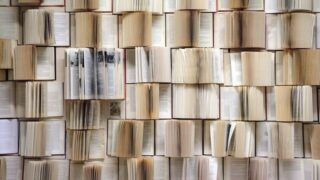【読書】「寄生生物の果てしなき進化」インフルエンザ~アレルギーまで

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、単純に寄生虫などが好きだから。文庫なのに税込み1,760円と高額なので、ちょっと躊躇したが購入。内容としては、サナダムシやエキノコックス、住血吸虫などの寄生虫系の内容を予想していたが、どちらかというとインフルエンザや麻疹、コレラ、ペストなどのウイルス性感染症の内容の方が多かった。
寄生生物の果てしなき進化(トォマス・アイヴィロ、2024年、草思社文庫)
2021年ハードカバーの文庫化
以下、本書で気になった部分をまとめる。特に「疫病と食料事情」の項は、非常に危機感を感じる内容であったので是非、目を通してもらいたい。本書では、寄生虫から細菌、ウイルスまでを、すべてパラサイトと表現している。
紹介する項目
・感染症の発症にはバランスが重要
・農耕による感染症の拡大
・なぜ人間には多くの感染症が存在するのか
・感染症の危険性とは何か
・人類が完全に駆除した2つの感染症
・インフルエンザが毎年大流行する理由
・疫病と食料事情 すぐそこにある飢餓
・ペットとアレルギー
感染症の発症にはバランスが重要
感染症が発生する(病気になるかどうか)は、宿主(人間)とパラサイト(ウイルス等)のバランスが重要と書かれている。保菌者が全員発病するわけではない。しかし、紛争や地震等で宿主側が不利(衛生面、栄養面、免疫面等)になると、パラサイトが有利となり発病する。日頃の環境管理が重要ということ。
【生活環境の向上が重要】
感染症抑制に最も貢献したのは、生活水準の向上である。栄養価の高い食事で健康になれば免疫機能も向上する。掃除や手を洗う体力もあり、不衛生な環境を改善できる。
農耕がすべてを変えた
農耕の発達により、人はひとつの場所に定住するようになった。それに伴い、人間とパラサイトが接する機会が増え、ヒトーヒト間での感染が容易となった。また、家畜を身近に置くことにより、動物―ヒト間の感染も増えていった。これは現在の都市化にまで連綿と続いており、不衛生、過度の密集、人口の多さは、パラサイトにとって天国である。
なぜ人間には多くの感染症が存在するのか?
答え:人間は体が大きく、パラサイトにとっては住む場所が豊富にある。他のパラサイトとの住み分けも効率よく行える。恒温動物のため体温が一定で、パラサイトは環境の変化を受けにくい。また、長寿であり個体数も多い。さしずめ、冷暖房完備の新築タワマンがそこら中に建っており、住みたい放題というところか。
感染症の危険性とは何か
何をもって「危険な感染症と判断するか」については、以下の様に書かれている。
・エボラ出血熱は危険とは言えない。なぜなら、感染力が低く患者の隔離が比較的容易だから。致死率だけで危険とは判断できない。
・コレラに感染するためには、少なくとも1億個の菌を体内に取り入れる必要がある。対して、結核はたった10個の菌からでも感染が確立する。
・ある感染症に対して、すぐに適切な治療が行えるかどうか、その感染症がどのような感染症か、すぐに特定できるかどうか、がカギ。
完全駆除に成功した2つの感染症
これまでに、人類が完全駆除に成功した感染症は、たった2つしかない。天然痘と牛疫である。天然痘は、かつて10億もの人類を死に追いやった感染症だったが、ワクチンの製造の容易さが功を奏して撲滅に至った。そして現在、世界中で天然痘ウイルスを保有しているのは、アメリカとロシアであるのは有名な話。
現在のほとんどの人類は、天然痘への免疫を持っていないのでバイオテロの危険性がある。世界保健機関(WHO)は、これら両国に天然痘ウイルスの破棄を求めているが断られている。理由は「何かあった時にウイルスのサンプルが無ければワクチンも作れないから」、とのこと。
インフルエンザが毎年大流行する理由
インフルエンザは、毎年世界各地で大流行している。なぜ天然痘のように撲滅できないのか?人は一度インフルエンザにかかると免疫を獲得し、“同じ”インフルエンザには一生涯かからないとある。
ではなぜ、毎年インフルエンザに苦しむのか?答えは、ウイルスが別の型に変異しているからである。ほんのちょっと変異するだけで、人間の免疫機能には“前回とは別のウイルス”と認識させることができるらしい。
【インフルエンザ小ネタ①】
Q:なぜインフルエンザが冬に大流行するのか?
A:正確には分からない。冬になると寒さで人間の免疫機能が低下するから、ともいわれたり。
【インフルエンザ小ネタ②】
インフルエンザは、北半球の冬⇒南半球の冬⇒北半球の冬と循環する。なので今年北半球で接種されるワクチンは、半年前に南半球で流行したインフルエンザの型を元に開発されている。
【インフルエンザ小ネタ③】
1918年に大流行し猛威を振るった”スペイン風邪”とは、インフルエンザのこと。皮肉なことに、スペインを感染源として大流行した“わけではない”。むしろ逆で、スペインは軽傷だった方。ではなぜ、スペイン風邪と呼ばれるようになったかというと、スペインが初めに報道したから。
疫病と食料事情 すぐそこにある飢餓
私が本書を読んで一番恐怖を感じたのが、この食料問題の項である。
以下は紛れもない事実である。
・トウモロコシ、米、小麦の3種で、全人類の栄養の50%を支えている
・たった15種類の作物で、全人類の摂取カロリーの90%を支えている
⇒Wikipedia「主食」で検索
・たった3種類のニワトリで、全世界の鶏肉の90%を支えている
これらは効率的な大量生産を目指し、より単一化を推し進めた結果である。数少ない品種に依存しているということは、これら数種類の作物やニワトリが一斉に疫病にかかった場合、人類はすぐにでも飢餓に襲われるということである。まさに、映画「インターステラー」の世界である。
単一化の結果、遺伝的多様性に欠けるので疫病が蔓延した場合、生き残れる種がいないということである。この問題への対策として、在来種の保存が挙げられている。
免疫の暴走(アレルギー)
アレルギーや過敏症などは、自己免疫疾患と言われ、免疫機能が正常に機能しなくなり自分の体を攻撃することである。この原因として、“衛生仮説”が紹介されている。その名の通り、衛生面できれいになりすぎて、バイキンと接する機会がなく出番のない免疫機能が、おかしな仕事を始めるというものだ。
ペットがアレルギー抑制となる?
自己免疫疾患への対策として、多様な自然環境や動物(ペット)と触れることが推奨されている。以前はペットがアレルギーの原因と考えられていたようだが、本書では事実は逆で、ペットや家畜が人間のアレルギーを抑制すると述べられている。
身近で役に立つ存在として、「犬」が推奨されている。このような動物を通して様々な、時にはマイナスとなるパラサイトに触れることが大事なようだ。特に生後1年以内に犬と同居していたかどうか、が大きなカギとなるとの記載もある。ちなみに猫でもいいのだが、猫は飼い主に触れる機会が犬より少ないので、犬が推奨されているようだ。
まとめ
以上、私が興味をもった内容をまとめてみた。寄生虫の話がメインかと思ったが、ウイルスや食料事情の話もあり、非常におもしろかった。1,760円の値段に尻込みしたが、十分に楽しめたと思う。新型コロナウイルスに関しての記述もあったが、2020年時点のものであり、コロナが終息した現在では、あまり役に立つ内容は書かれていなかった。