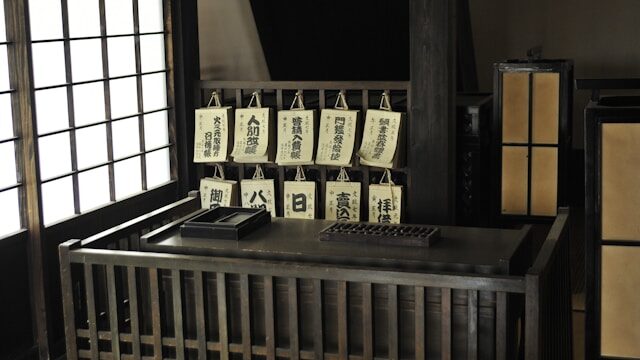「二○三高地」乃木希典愚将論に終止符を!

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、乃木希典(のぎ まれすけ)の評価について知りたかったからだ。何度となく持ち上がる「乃木希典は名将か愚将か」という論争について、自分でも調べてみたいと思ったのである。
二○三高地 旅順攻囲戦乃木希典の決断(長南政義、2024年8月、角川新書)
司馬遼太郎の影響
私の中の「乃木希典像」は、司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」から得られたものである。そして司馬遼太郎は、相当に乃木希典を酷評しており、作中での書かれ方にも影響していたといわれている。そこで司馬遼太郎のフィルターを通さない目線から乃木希典を知ってみたいと思った。
実際に本書の冒頭でも、司馬遼太郎の「坂の上の雲」の発行が、当時名将と言われていた乃木希典の評価を大きく落とす契機のひとつになった、と書かれている。いずれが正しいのか・・・
本書を読んだ感想
非常に多くの知識が得られた。旅順攻囲戦の戦況や、その時の背景(細かい内部事情)などが詳しく解説されており、実際に作戦に参加しているような臨場感を得られる。結論として、本書では乃木希典を「名将」と評価している。
日露戦争と旅順要塞攻略の概要
日露戦争や旅順要塞攻略について、基礎的な知識が無い人のために簡素に説明する。日露戦争の原因は、ひと言でいえば中国支配をもくろむ日本にとって、ロシアが目障りだったということだ。
戦争期間
1904/2/6~1905/9/5(明治37年2月~明治38年9月)
約1年半と、それほど長期間の戦争ではない。旅順攻囲戦は、この約1年半の戦争のうち、ちょうど中間期にあたる、1904/7/30~1905/1/1までの約半年の戦である。
戦勝国
日本の勝利。この日露戦争とひとつ前の日清戦争で、立て続けに大国に勝利したことが、日本という国を勘違いさせる原因となり、約40年後に同じノリで望んだ太平洋戦争でコテンパンにやられたのは、みなさんもご承知のとおり。
旅順要塞攻略の位置づけ
旅順要塞は中国の遼東半島の南西端に構築されたロシア軍の要塞である。日露戦争の雌雄は北の遼陽、奉天方面で決せられる見込みであったため、本来であれば決戦場と真逆の半島先にある要塞など無視しておけばよかった。事実、陸軍も開戦当初は遼東半島を分断し、旅順要塞を孤立させる程度で、攻略する必要性はないと考えていた。しかし、状況は徐々に異なって来る。(下図、赤丸が遼東半島の位置)

旅順要塞攻略の必要性
ではなぜ、旅順要塞攻略が必要となって来たのか?それは以下の理由による。
①旅順港には、ロシアの太平洋艦隊が逃げ込んでいた。旅順港は要塞に守られていた為、日本の海軍はこれを撃滅できなかった。(港内への封鎖は出来た)
②ロシアのバルチック艦隊が、援軍として遼東半島に向かっていた。
③バルチック艦隊到着までに、旅順港内の太平洋艦隊を撃滅しなければ、日本海軍は挟み撃ち及び数の上からも、敗北する可能性が高かった。
④制海権を失うと日本からの補給もままならず、戦争に負ける可能性が高くなる。
これらの理由から、旅順要塞を是が非でも攻略する必要が出てきたのである。そしてこの、旅順要塞攻略の指揮を任されたのが、日本陸軍第三軍、軍司令官の乃木希典であった。
第三軍に与えられた使命
旅順要塞攻略にあたり、乃木希典率いる第三軍に与えられた命令は、
バルチック艦隊到着までに、
①旅順要塞を陥落させること
②旅順港内の太平洋艦隊を無力化すること
の2つであった。優先順位としては②が優先事項であり、②さえ満たせれば必ずしも①を行う必要はなかった。実際の戦いでも②を先に達成し、その後①の完遂となっている。
乃木希典評価の論点
このような戦争状況の中、本記事の本題である乃木希典の評価については、以下の点が議論のポイントとなる。
・旅順要塞攻略に、相当の時間を要したこと(当初予定を4.5ヶ月オーバーした)
・旅順要塞攻略に、多大なる人的犠牲を生じさせたこと(戦死者約1.4万人、負傷者約4.3万人)
※日露戦争全体での、日本軍の戦死者は約5.5万人、負傷者は15.4万人。よって、戦死者の25%を旅順要塞攻略で出したことになる。
これらの期間と犠牲は妥当だったのか?ということである。
日露戦争開戦から旅順攻略の軌跡
ここから日露戦争開戦から、旅順要塞陥落までの戦いの流れを記載する。
【1】開戦から第三軍派遣、攻囲線完了まで
明治37年(1904年)2/6 日露戦争開戦
5/2 乃木が第三軍の軍司令に任命される
5/28 第二軍が大連占領、遼東半島の分断、旅順要塞を孤立させることに成功
6/6 第三軍、遼東半島上陸
6/26 第三軍、歪頭山、剣山を占領
7月以降 バルチック艦隊出撃の報を受け、旅順要塞攻略が急務とされる
第三軍に対して、大本営、海軍から一刻も早く旅順要塞を攻略するよう圧力がかかり始める
7/18 8月末までに旅順要塞攻略を完了させることを、第三軍と満州軍司令部とで協定
7/26~28 ロシア軍の前進陣地の攻略
7/30 旅順要塞の攻囲線を確立させる
8/13頃まで 攻囲線周辺の山々などの占領に時間を費やすこととなる
以上が前哨戦となるが、ここまでの戦闘での死者は1,290名、負傷者5,711名であった。
【2】第一回総攻撃(8/19~8/24)
6/6の遼東半島上陸から進軍し約2か月、満を持しての総攻撃となるのだが、この攻撃は失敗する。第一回総攻撃での死者は3,972人、負傷者は10,765名であった。死傷者数は、戦闘参加員の約31%にもおよぶ事態となった。死傷の原因は、機関銃による殺傷である。これは強襲法(後述)の採用が原因と考えられる。
第一回総攻撃失敗の原因
第一回総攻撃の失敗の原因は、第三軍の攻撃対象が、敵の最も防御力の強い場所であったため。なぜこのような結果となったのか?
・作戦完了までの時間が無いので、時間のかかる他の戦術を選択できなかった
・強襲法の選択(歩兵に長距離を突撃させる⇒敵からすれば格好のマト)
・国力、生産能力の脆弱による砲弾の不足
・砲撃数の割に、要塞に有効なダメージを与えられなかった
攻撃は失敗に終わったが、多くを学ぶ結果となった。
【3】第二回総攻撃(10/26~10/31)
正攻法への転換(乃木の決断による)
第一回総攻撃では、強襲法を選択し多大なる犠牲が生じたため、正攻法への転換を図った。正攻法とは、塹壕を掘り進め敵陣地に徐々に近づく戦法。最後に突撃を行うが、突撃距離は強襲法に比べてずっと短い距離(40~100m)で済む。欠点は、塹壕を掘るのに時間を要すること。
このように手法を変えた第二回総攻撃も失敗に終わる。第二回総攻撃での死者は825人、負傷者は2,812名と第一回総攻撃(死者は3,972人、負傷者は10,765名)から劇的に減少した。要因は正攻法への転換であり、それを決断した乃木の采配は評価されるべきとある。
第二回総攻撃失敗の原因
・砲弾不足、とにかく旅順攻囲戦は、砲弾不足に苦しむ戦いであった
・敵堡塁の外濠の突破が困難(濠の幅が広く、深く高さがあり突破が容易ではなかった)
・濠攻略中にロシア兵からの機銃掃射、手投げ弾による死傷者が続出した
【4】第三回総攻撃(11/26~12/5)
ついに旅順攻囲戦に決着がつく、第三回総攻撃が実施されることになった。バルチック艦隊の到着が翌年の1月上旬と予想されていたため国を挙げて、この総攻撃に賭けていたのである。満州軍総司令部からも「多大の犠牲」をいとわず目的を達するよう要請が来ていた。
第三回総攻撃での死者は5,020人、負傷者は11,726名と第一回総攻撃(死者は3,972人、負傷者は10,765名)を上回る損害が出た。最後の決戦がいかに激戦であり、「多大の犠牲」を出したかが分かる結果となった。
第三回総攻撃の目標
第三軍司令部は、あくまで要塞北東部を主たる攻撃目標としていた。だが、残念ながらこれに失敗する。失敗の要因は、やはり堡塁の突破が困難なことであった。そして11/27に、二○三高地へ攻撃の主力を向ける命令が下された。
【5】最終決戦!二○三高地
11/27日から二○三高地の攻略戦が始まるが、一時は奪取したものの二度までもロシア軍奪い返され12/1まで一進一退の攻防が続く。ロシア軍も二○三高地にありったけの人員を注ぎ込み、決戦の様相を呈して来る。このように第三軍が苦戦する中、12/1にあの人物が満州軍司令部から到着することになる。
児玉源太郎の到着
12/1に満州軍総司令部の総参謀長である児玉源太郎が、旅順に到着する。目的は、親友である乃木を激励、支援するためと書かれている。そして、児玉源太郎到着後は戦力を二○三高地に集中し、12/5についに二○三高地を陥落させることができた。
旅順戦の一段落
二○三高地を日本軍が占領したことで、旅順攻囲戦は一段落した。なぜなら、二○三高地からは旅順港が一望でき、ここからの砲弾射撃で旅順港内のロシア艦隊を無力化することに成功したからである。そのため、これ以降は無理な犠牲を強いることなく戦いを進めることができるようになった。
旅順要塞陥落
二○三高地攻略から約1か月後の翌年の1/1に旅順のロシア軍は降伏し、旅順での戦いは終わった。ロシア軍降伏の理由は、二○三高地での決戦に戦力を投入しすぎて消耗戦になり、これ以上戦いを継続できなくなった、というのが要因である。しかし、考えれば7/30の攻囲完了後、約5か月間にわたり一切の援軍も補給もなく、ロシア軍はよく戦ったと思う。
乃木希典の評価
長々と旅順攻囲戦について経過を書いてきたが、本来の目的である乃木希典の評価についてはどうなのだろうか。結論として、本書では乃木希典は「名将」と評価されている。その理由として、
・当時、日本軍として要塞攻略の研究が不十分であった
・砲弾が慢性的に不足していた。
・主砲弾の威力では旅順要塞の防護コンクリートに有効なダメージを与えられなかった
・作戦遂行についてバルチック艦隊到着までという、大きな時間的制約を受けており手段を選んでいられなかった
という、不利な状況で戦っていた。にもかかわらず、
・各師団長から不満の声が上がらなかった
・海軍にも配慮した作戦を行っていた
・戦時国際法を尊重していた(戦闘前の降伏勧告等)
これらの点を、考慮すると「愚将」という評価がどこから出てくるのか、というところである。
秋山真之の評価
本書には、同時代を生きた第三者の乃木希典への評価として「坂の上の雲」の主人公の一人でもある海軍参謀、秋山真之の評価が記載されている。そこで秋山は、「要塞という地の利を持っているロシア軍に日本軍が対抗するには、人的物量に拠るしかなく、人的被害が拡大することは驚くことでも批判することでもない。乃木希典の戦い方は、最良戦策」と評価している。
まとめ
このように、乃木希典への近年の評価は「名将」論が優勢となっている。しかし、残念なのは、「坂の上の雲」という乃木希典の誤った評価をした本が、これからも出版され続けることである。そういう人々は、以前の私の様に「乃木希典って無能だったの?」という気持ちを持ってしまう。
本来であれば。作者である司馬遼太郎本人が、乃木希典への評価を自ら改めるべきだろうが、残念ながら故人となっているので、どうしようもないということだ。「坂の上の雲」を読んだ人は、是非とも本書も読んでもらいたい。
後日談、バルチック艦隊との戦
さて、これほどまでの犠牲を払って旅順のロシア艦隊を無力化したのはひとえに、バルチック艦隊襲来に備えたものであった。そして、肝心のバルチック艦隊と日本海軍の戦いはどうだったかというと・・・、あっけないほど日本の完全勝利に終わっている。(日本海海戦)日本が強かったというのもあるが、相手が超長距離の航海の果ての戦いで、ヘロヘロになっていたという要因もある。
実際、バルチック艦隊は、スウェーデン近くのロシアの港から、西回りでヨーロッパを超え、南下しアフリカ喜望峰を回って、33,000キロにもおよぶ半年以上の大航海の末に、日本にたどり着いている。その後に戦えと言われても、士気も上がらないだろう。もっとも、そんなことは結果論に過ぎず、旅順要塞攻略が無駄であったということは決してない。