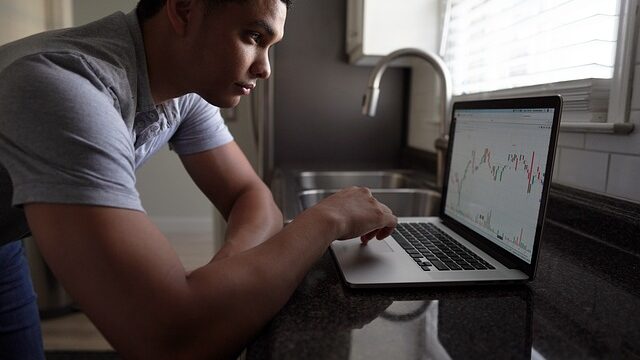「論語と算盤」渋沢栄一ってどんな人? お金に対する考え方

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、以前に紹介した福沢諭吉の「学問のすすめ」と同じく、「まぁ、有名な著書だし(読んだことがあるという)アリバイ作りのために読むか」という「ファスト教養」的感じである。また、新一万円札の顔でもあるので、どのような人物なのか知りたい、という思いもあった。「学問のすすめ」同様、読みやすさ、理解しやすさを重視して現代語訳とした。
現代語訳 論語と算盤(渋沢栄一、2010年、ちくま新書)
渋沢栄一について
新一万円札に採用されるということで、名前を聞いた時「渋沢栄一?誰それ?」というのが私の正直な感想であった。勉強不足で申し訳ないが、まったくデータに入ってない人物であった。本書では、渋沢栄一が設立にかかわった会社は約480社、500以上の慈善事業にも関わり「日本資本主義の父」と呼ばれている、と書かれている。
生きた時代としては、天保11年~昭和6年(1840年~1931年)91歳没となり、江戸末期から明治、大正、昭和初期まで生きた人物である。旧一万円札の福沢諭吉(天保5年~明治34年(1835年~1901年)66歳没)とは生きた時代は同じであるが、福沢の方が30年も早く亡くなっている。というか渋沢が長寿なのだ。
現在、渋沢栄一といえば“妾の数”という悪いイメージが先行しているようで、ヤフーの検索予測でも上位にあがってくる。その点については最後に書く。以下、私が論語と算盤から気になった点をまとめる。
商売(事業)で日本を強くしようとした
渋沢栄一は元々は役人(官僚)であったが、当時の日本は列強諸国に比べて「商売」が上手ではなく、国を強く豊かにするためには商売(事業)というものを強くしていかなければならないと思い、野に下った。その時、拝金主義に陥らないような歯止めとして、孔子の「論語」を教科書とした。
後輩にどう接するのか
渋沢は「敵国や外患が無いと国は亡ぶ」と述べている。その例えとして後輩に接する時に、①常に後輩の見方をして守ってやる、②常に後輩の敵の様に厳しく接する、どちらがいいのかを問うている。
①は、確かに人望は得られるかもしれないが、後輩は(常に先輩が守ってくれるので)自堕落になると言い、②は先輩にドヤされないために自助努力し伸びる、結果的には②の方が良いと書かれている。悩ましいところだ、令和の今ならおそらく後輩は、会社を辞めるか自分がパワハラで呼び出されるだろう。。。
本当の経済活動とは
本書では、本当の経済活動とは「社会のためになる道徳でないと長く続かない」と述べられている。お決まりの献身精神かと思われがちだが、同時に「儲けてお金持ちになりたい」という気持ちも重要だ、と書かれている。要は両者のバランスである、
自分さえ儲かればいいという考えでは、決して長続きしないと断言している。対策として必要なのは、道徳という要素をバランスよく加えていくことである。
お金の扱い方
お金を大切にすることも重要だが、同じぐらい必要な時に上手く使うことも重要と書かれている。よく集めて、よく使い、社会を活性化させる。金は天下の回り物ということか。ここで「よく使う」とは、金額の多寡ではなく「正しいことに使う」と記されている。
「お金を大切にする」の意味をはき違え、ひたすらため込む守銭奴になることを注意せよとある。私的には、少し耳の痛い話である。
利己主義への警鐘
西洋文化が入るにつれ、人々は利己主義に走り、「目的のためには手段を択ばない。自分が儲かればそれでよい」という考え方に取りつかれているが、そういったものは「成功の意味を誤解している、認めるわけにはいかない」と強く否定している。
こちらの記事で紹介した「ファスト教養」と同じく、今の令和で言われていることと、同じである。すでに明治、大正頃から日本にも、そのような傾向が出始めていたということか。この辺りの「道徳感」については、渋沢も福沢も新渡戸も一様に同じような警鐘を鳴らしている。
ただ、渋沢は事業家ということもあり、貧富の格差をなくすことはできないと述べている。人が一生懸命に物事に取り組むためには競争が必要。「競争とは勉強や進歩の母」と考えている。この点、先ほどの後輩への接し方に通ずるものがある。
自己責任論の否定
渋沢が東京市養育院の職員へ述べた講演の事がかかれている。養育院とは今でいう生活保護者の支援施設のようなものだ。渋沢はここに収容されている人たちを「自業自得の人」、今でいう自己責任の結果としている。だが、「自業自得だからと言って同情を持って接しないのは、よくないことだ」とも述べている。
令和の今は自己責任論が跋扈している。私も自己責任論を100%否定する考えは持っていないが、すべて成功も失敗も個人の責任と割り切って、切り捨てていいのかという疑問もある。そういう考えで、この先日本はどうなるのか?という不安もある。
まとめ
事業家ということもあり、お金や事業に対する考え方についての記述が多い。その点が「学問のすすめ」と大きく異なる点である。より実践的とでも言おうか。最後に、「成功や失敗といった価値観から抜け出して、自立した正しい生き方をすれば、価値のある生涯を過ごすことができる」と締めくくられている。
妾問題
そんな立派なことを述べている、渋沢栄一の唯一?の欠点は女性にだらしなかったことだ。具体的な妾の数は書かれていないが、子供は30人以上いたらしい。本人も自分の人生を振り返って、「婦人関係“以外”は恥じることのない生涯だった」と語っており、女性問題については、自覚しているようだ。