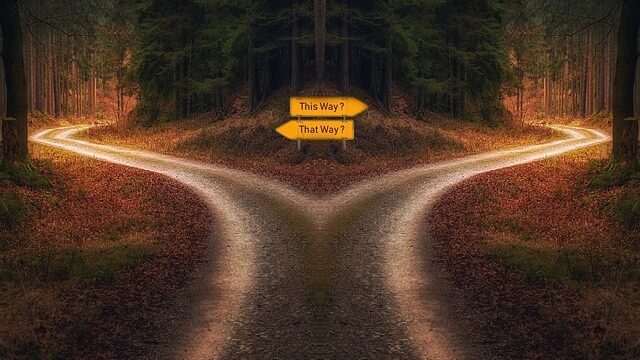「円高・円安」あなたは、ちゃんと理解しているか?

為替について、理解しているか
株式市場と同じぐらい経済ニュースで取り上げられる為替の動向。あなたは為替(円高・円安)について、どこまで理解しているだろうか。もし、会社で部下や後輩から、
①1ドル100円から120円になったのって円高・円安どちらですか?
②日本にとって円高・円安どちらがが良いのですか?
③円高、円安について、分かるように教えてください
と矢継ぎ早に聞かれて答えることが出来るだろうか。私個人としては、①、②ぐらいまでは大丈夫だと思う。だが③については、私自身もよくわかっていない。「人に教えると、教えた側の理解度も進む」とは、よく聞く話なので他人に教えるつもりで自分なりにまとめてみた。
どちらが円安・円高なのか?
まずは、「①1ドル100円から120円になったのって円高・円安どちらですか?」について考える。ここでは、なぜそうなるのかの理由は考えない。答えだけを知ることにする。
現在、1ドル=100円として、将来的にAとBのどちらが円高か、あなたは分かるだろうか。
A:1ドル=120円
B:1ドル=80円
直感とは逆が答え
直感的には、「80円よりも120円の方が高いので」Aが円高と言いたいが、残念ながらBが円高である。これが為替を分かりにくくしている元凶であると私は考えている。私もいちいち脳内で「確か、高いと安いは逆だったから・・・」と一瞬考えてしまい、即答できない。
当然、「なぜ”安い”方の80円を円”高”」というのか理由も説明できない。とにかくここでは、1ドル100円だったものが、1ドル120円になるのが“円安”、1ドル80円になるのが“円高”と覚えておこう。
「なぜ?」の部分は、これからじっくりと解説していく。
日本にとってどっちが良いのか
これについては多くの人が、直感的に理解できるだろう。答えは、一長一短である。
円安は、輸出企業(売り手の日本)に得で、輸入企業(買い手の日本)に損
円高は、輸出企業(売り手の日本)に損で、輸入企業(買い手の日本)に得
となる。
円安になると誰が得をするのか
円安について考えると、1ドル100円 ⇒ 1ドル120円になった場合、
5ドルの商品を売れば、代金として100円×5=500円だった所が、120円×5=600円もらえる。だから輸出業者は儲かる。逆に、5ドルの商品を買えば今まで500円だった代金が600円支払わなければならないので、輸入業者としては出費が増える(損をする)。
おそらく、ここまでは多くの人が着いてこれる。問題は次である。
円の相対的価値について考える
いよいよ、ここから円高・円安について詳しく考えていく。まずは、円高・円安の定義を確認する。円高・円安についてネットで調べると、必ずと言っていいほど
・円高とは、円の他通貨に対する相対的価値が高い(多い)状態
・円安とは、円の他通貨に対する相対的価値が低い(少ない)状態
といった類の回答が出て来る。私も含め、多くの人がここで頭がショートし脱落する。「他通貨に対する”相対的価値”ってなに?」となる。
分解して考える
一気に考えるので難しくなる。ここは分解してひとつひとつ考えることにする。
円高とは、
①円の他通貨に対する
②相対的
③価値が高い状態
ということになる。
①他通貨とは
他通貨とは、円以外の通貨。すなわち、ドルやユーロやポンドのことを指す。通常、「円高だ、円安だ」とニュースで騒がれるのは、ドルに対してのみなので、他通貨=ドルと考えて差し支えないだろう。
①結論
他通貨とは、具体的には「ドル」のことである。
なぜドルなのか?それはドルが世界でもっとも信用され、多く利用されている通貨だから。これを「基軸通貨」と呼ぶ。
②相対的とは
相対的をネットで調べると、「相対的とは、何らかの比較の上で成り立つ様子や評価のことである。単独では成立せず、2つ以上の比較対象を必要とする。」
ポイントは、「単独では成立しない。2つ以上の比較対象を必要とする」という所である。また、相対的とは立場が変わればものの見方(評価)は変化するというものである。以下の例で考える。
身長は高いのか?低いのか?
例えば次の例を考える。
・A君の身長は160cm
・B君の身長は170cm
・中学で同級生だった二人が、高校3年生の時に再開したとする
・再開時のA君の身長185cm
・再開時のB君の身長175cm
A君からすれば、「B君背が低くなったなぁ」という感想である
B君からすれば、「A君背が高くなったなぁ」という感想である
高い低いという真逆の表現だが、お互い言っていることは間違っていない。これが「相対的評価」というものである。
②結論
相対的とは、”お互いの立場”から相手を評価した内容となる。その内容は、必ず相手とは真逆となる。立場が変わればものの見方(評価)は変化するのだ。
③価値の高い状態とは
重要なポイントは、高いのは「価格」ではなく、「価値」ということである。金額の多寡でないことに注意しよう。
身近なものに置き換えて考える
ドルと円と両方共お金の関係だから、いまいちイメージが湧かないのだろう。これを品物に置き換えるとわかりやすいと思う。例えば、ドルをエルメスの高級バック“バーキン”、円を”ダイヤモンド”に置き換えてみる。
【身近なものに置き換えて考える】
・ドル ⇒バーキン
・円 ⇒ダイヤモンド
バーキンの価値の変動
・2025年にエルメスのお店に行くと、ダイヤモンド5粒でバーキン1個と交換してくれる
・3年後の2028年にお店に行くと、ダイヤモンド3粒でバーキン1個と交換してくれた
・この変化をどう評価するのか?
バーキンの価値が下がった
これは直感的に理解できるだろう。2025年にはダイヤモンド5粒分の価値があったバーキンが、2028年には3粒分の価値しかない。これはバーキンの価値が下がったといえる。
ダイヤモンドの価値が上がった
こうも考えられないだろうか。ダイヤモンド1粒の価値が上がったのである。2025年であれば5粒必要だったところが、2028年では(ダイヤモンドの価値が上がったので)3粒でバーキンと交換できるようになったのである。
あとは、バーキンとダイヤモンドをドルと円に戻すだけである。ドルの価値も変化する、円の価値も変化することが分かってもらえたと思う。
③結論
・バーキン(=ドル)とダイヤモンド(=円)、それぞれの価値は独立して変化する
・ドルと円の価値は、日々刻々と変化する
・お互いの価値が、釣り合ったところで交換が成立する
最後のおさらい
最後のおさらいとして、次の3つのパターンを考えてみる。どの状態が円高(円の価値が高い)で、どの状態が円安(円の価値が低い)だろうか?
①1ドル=25万円
①1ドル=3,000円
②1ドル=10円
マイクに聞いてみる
あなたは1ドル欲しいとする。アメリカ人のマイクに円とドルを交換してくれるよう、お願いしてみる。
①の場合
円とドルを交換して欲しいだぁ?そんな、しょっぼい円とドルを交換して欲しかったら、25万円分用意しな。それぐらいじゃないと1ドルとは釣り合わないね。
②の場合
1ドルなら3,000円かな。
③の場合
円と交換してくれるんですか?それなら1ドル10円あれば十分ですよ。
さて、マイク目線(ドル目線)で、どれが一番円の価値が高い(円高)だろうか。(答えは③)
まとめ
以上、長々と円高・円安について書いてきたが、最後にまとめてみる。
・円高:円の価値が高い。よって、少ない円でドルと交換できる
例えば、1ドル得るのに50円出せばよい状態
・円安:円の価値が低い。よって、ドルと交換するのに大量の円を必要とする
例えば、1ドル得るのに100万円必要な状態
先ほどまで、1ドル=80円の場合、「価格は安いのに、なぜ円高なの?」と不思議に思っていたが、今ならなぜ80円が円高なのかもわかるだろう。
1ドル360円時代もあった
戦後、為替は1ドル=360円という固定相場でスタートした。それが、1973年から今のような変動相場(日々、為替レートが変化する)に移行になった。そして2025年8月現在、1ドル=147円である。
ここまで読んだ方ならもうわかるだろうが、当時よりはずっと円高になっている。円の価値は上昇したということだ、それだけ、国際的に円=日本と言う国が認められたということだろう。
円高が正義ではない
勘違いしてはいけないのが、円の価値が高い(円高)が無条件で良いかというと、そうではないということである。
「円の価値が高い」というと日本が優れているように感じるかもしれないが、円高一辺倒が日本のためになるかと言うと、そうではない。円高になると輸出企業の業績は下がることは述べた。日本は、材料を輸入して製品を輸出し稼いでいる。輸入と輸出、両方が必要となるので一方的な円高は歓迎できないのである。同じように、一方的な円安も望まれない。
S&Pやオルカンにも影響
新NISAで米国のS&Pやオルカンを購入している人も多いだろう。こういったドル建ての海外商品は、まともに為替(円高・円安)の影響を受ける。S&Pやオルカンの場合、「円安」となった方が換金率は上がるので、日本円での手取りの利益が増えるのである。
便宜上、「円の他通貨に対する相対的価値が高い、低い」と表現しているが、「高い」ことが、無条件で良いというわけではないのである。