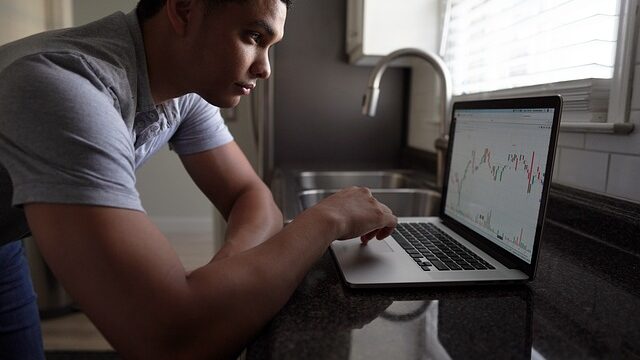「駄菓子屋の儲けは0円なのになぜ潰れないのか?」個々に特化?

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、単純にタイトルの答えが知りたかったからだ。実際には、潰れる駄菓子屋もあるが潰れていない駄菓子屋についてその理由が書かれているといった感じだ。駄菓子屋のすべてが潰れないような印象を与えるが、そうではない。少しタイトルを盛っている。
駄菓子屋の儲けは0円なのになぜ潰れないのか?(坂口 孝則、2025年4月、SB新書)
この本をお薦めする人
私のように純粋に「なぜ?」を知りたい人をはじめ、いわゆる脱サラして何か店舗経営を始めたいという人にはヒントになるかもしれない。多くは小規模資本の店舗事例が紹介されているので、個人資本で始める人には参考になるだろう。
本書を読んだ感想
本書では駄菓子屋の他にも、商店街の靴屋やタバコ屋、的屋、占い店、焼き芋屋、激安居酒屋など、マイナー店舗や採算が合うのか?という業種について生き残っている理由が書かれており面白かった。
店舗がつぶれないカラクリ
本書で紹介されている各店舗の生き残りのカラクリのいくつかを紹介する。もう一度書くが、実際には潰れない訳では無い。「相当数の店舗が淘汰されている」ことも事実であるが、しぶとく生き残っている店舗の戦略が紹介されている。その要因のひとつに、ライバル店舗が減っているというのもあるだろう。
飲食系店舗
駄菓子屋:小学校近く等立地条件で客が集まりやすい。仕入れ単価が安く、自宅兼店舗かつ家族経営であれば、人件費もかからないから。
酒屋:店舗に併設した立ち飲みスペースが好調。自店のお酒を提供できて一石二鳥。
スナック:根強い人気と常連客に支えられている。意外と回転率が高い。
成功の秘訣:人とのつながりを重視し、常連客やリピーターの獲得に力を入れている。
商店街系店舗
傘屋:コンビニのビニール傘との差別化。高級路線かつ修理に力を入れることで一定の客を確保。高級傘ならおいそれと捨てるわけにもいかない。修理して使う。そういった客の買い替え需要も取り込んでいる。最近は日傘需要も好調。
靴屋:靴を売るよりも「修理」に活路を見出している。大型店舗は売るだけなので、修理需要を取り込んでいる。オーダーメイドの高級靴に活路を見出す店もある。
タバコ屋:品揃えの豊富さで勝負。自動販売機で扱わないような多種多様なタバコ、例えば外国産タバコや葉巻などを扱い集客につなげている。ここでしか買えない系の戦略。
成功の秘訣:無益な大手との競合は避けて、例えば修理など特定のニーズに特化したニッチ需要で勝負している。繰り返し修理や新規販売などで特定の客と10年以上の付き合いを継続する。
季節限定の商売
焼き芋屋:とにかくコストが安い。固定店舗がなく、必要なのは軽トラと芋、燃料費と人件費ぐらい。芋を焼く設備の技術進歩もあり調理に関する経験も必要なくなってきている。シーズン限定なのが欠点だが、冷やし焼き芋などで夏への活路もあるかも。
的屋:圧倒的にコストが安いのが、綿あめ。バーナーと砂糖だけ。繁忙期は正月。その他、花見、夏祭りなどが主な収入源。それ以外は建設現場などで働く人もいるとか。的屋一本では厳しいのだろうか。現代版としてキッチンカーへの転換もあるらしい。
スキー場:夏はその自然を活かしたバーベキュー会場、キャンプ場、森林浴やトレッキングなどいくらでも活用方法はある。
メインから1本裏のお店
靴磨き:最近はスーツのカジュアル化も進み、革靴自体の需要がへり逆風。それでも革靴にこだわる人の一定の需要はあるようだ。また、一度靴磨きを利用すると癖になるというか、その職人芸にハマって行く人が多い。そういう常連を地道に積み上げていく。
占い師:こちらも姓名判断、恋愛相談などの一定の需要はある。上手く行くと会社の経営者などとのおつきあいも広がっていく。もうだいぶ前になるが、某ベテラン女性お笑いコンビの一人に占い師が付いていて世間を騒がせたこともあった。
薄利多売系
激安居酒屋店:とにかく回転率で勝負。へぇ~と思ったのが、人手不足で当たり前になりつつあるタッチパネル注文やQRコード注文は、逆に売上減になっているらしい。お客は店員から積極的に声掛けしないと追加オーダーをしてくれないというのがその理由。人件費削減と注文減とどちらがロスとなるのか見極めが必要。
ソーシャルゲーム:私自身はスマホ世代ではないので、ソシャゲはやらないが基本プレイ無料が通常である。これらは概ね2~5%の課金ユーザーで成り立っているとのこと。たったそれだけで、開発費や広告費をカバーし利益まで出すのだから、いかほど課金しているのか非常に興味がある。
まとめ
共通事項
これまで紹介してきた店舗(ソシャゲは除く)に共有するのは、
・大資本ではない小規模店舗が多い
・商売の維持費が比較的安い
・世の中から無くならない一定の需要をターゲットとしている
・常連客に支えられている
といった感じだろうか。
新規参入はどうなのだろうか
では、こういった業種に新規参入した場合はどうなのだろうか?実践へのヒントは少し書かれていたが、具体的なことにはあまり触れられてなかった。例えば、その業界(靴屋など)の先行きは明るいのか。既に飽和状態なのか。新規参入した場合、店が軌道に乗るためにはどれぐらいの間耐えられる資金が必要なのか。これらの情報については、書かれていなかった。
確かに一定の需要は無くならないだろうが、少ないパイの奪い合いと言うことも予想される。また、同業店舗の分布バランスなども重要となって来るだろう。駅前に同業種が1店参入しただけで、均衡していたバランスが一気に崩れてしまうなど、絶妙なバランスの上に成り立っていたということも考えられる、
この辺り本当に商売は難しいと思う。本書にも書かれていたが、やはり小さく始めてとにかく生き残ることを最優先にするのが重要だろう。無理と分ければ深入りせず、早めの撤退も必要かもしれない。