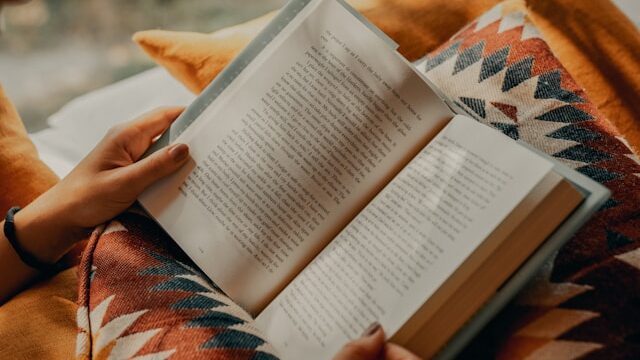「映画を早送りで観る人たち」現代の価値観に触れてみる

この本を読もうと思った理由
私がこの本を読もうと思った理由は、以前に紹介した「ファスト教養」の中で、この本のことが書かれていたからであった。同様のジャンルを別の視点から再度確認してみようと思った。ちなみに、私は本書で紹介されているような、倍速視聴はやったことがない。
映画を早送りで観る人たち(稲田 豊史、2022年4月、光文社新書)
まとめ
本書の内容を簡素にまとめると
・若者の一定層は、映画を早送りで観る
・その動機は友人との会話のために、知識として知っておきたから
・映画やアニメそのものを楽しむという目的は薄い
・膨大な情報を処理する時間が圧倒的に足りない
・効率よく情報処理するためコスパ重視にならざるを得ない
・そんなにしんどいなら、辞めれば?と言いたいがその選択肢はない
映画を早送りで見る人たち
本書では、映画を早送りする人たちに対するインタビューが掲載されている。そこでは単純に早送りで「すべて」を見るのではなく、目的のシーンまで飛ばしてそこから倍速で観る、という回答もあった。もはやそこまで削るなら「観なくてもいいのでは?」と言いたくなる。事実、著者が「観ないという選択肢はないのか?」と質問しているが、彼らはそれでも「観る」と答えている。
目的はアリバイ作り
そこまでしてでも「観る」と答えた人の理由は、「友達との話題に出た時に観たことがある」と話を合わせるためのアリバイ作りである。これは私自身も、「学問のすすめ」や「論語と算盤」を読んだ理由で書いているので、その気持ちは理解できる。ただ、私の場合は少なくとも「すべて」読んでいる。
飛ばしまくりだと理解度も大幅にダウンすると思うのだが、その部分に関しては問題ないのだろうか?この辺りは、映画を見る目的が友人との話題を合わせる程度なので、「すべてを見る必要はないし、詳細まで理解する必要もない」という判断なのだろう。
取りあえず最終話を見る人たち
インタビューの中では、ドラマを「最初の3話まで見て、次に最終回を見た」という人もいる。とにかく結末が先に知りたいというのが、その理由である。話数の多いアニメや漫画に関して言えば、私はこの考えには同意できる。
「興味ない」で済ませる選択肢は?
たとえ有名で旬な映画だとしても、自分に興味がなければ無理して観なくてもイイと思うのだが、現在の価値観からするとダメなのだろうか?「アニメ?興味ないから観ない」この一言で処理する方が、無理して倍速で何十話もあるアニメ作品を見るよりは、よっぽど「コスパがいい」と思うのだが・・・
サブスクが雑な扱いを加速させる
人はタダで手に入るものを大事にしない、と書かれている。ネトフリやアマプラなどは定額見放題である、なのでそこで配信される映画などは基本タダという感覚になってしまう。タダで何度でも見れるので、テキトーに観てもいいだろうという気持ちが芽生えてくるとある。なるほどよく分かる。ちょっとつまみ食いして、面白くなければヤメというのは非常に理解できる。
すべての説明を求める人たち
本書では、「状況やその人の心情を、1から10まで説明して欲する作品が求められている」と紹介されている。この場合、沈黙の間や、暗喩や皮肉等の表現を避け、直接的なセリフで「好きだ、嫌いだ」という表現が昨今の風潮として求められている。
他にも、「うぅっ、ぐっぁ!」などと言う表現ではなく「ぐわぁ~斬られた、痛い~」という感じだ。わざとらしすぎて興ざめしそうなのだが。。。この辺り、作り手と消費者側での意識の乖離が発生している。
理解できないのは作品のせい
わかりやすい作品が求められる理由として、視聴者側が「わからなかった、理解できなかった」という事象を認めたくないから、とある。さらに、「理解できない作品=駄作、つまらない作品」と位置付けられる傾向にある。さすがにこれは、消費者側の無茶理論の様な気がするのだが、これが現代の流れなのだろうか。
映画ではないが、安部公房の小説などは意味不明、理解不能などいくらでもあるのだが。。。私など「壁」とか意味わからなさ過ぎてリタイアしたものだ。こういうのは、次に書くコスパの観点からからも避けたいのだろう。
コスパ重視で失敗は何としても避けたい
現在の(一部の?)若者は、とにかく自分たちは学ぶべきことが多いと感じているようだ。そのため、どうしても効率(コスパ)重視にならざるを得ない。まぁ、この思考は理解できる。そのため、失敗=無駄な行動をとにかく避けるようになる。
結果、最適解リストを求めてしまう。この辺り「ファスト教養」でも書いたが同じような構図のようだ。
おっさんからのアドバイス
一応、無駄に人生を経験した世代からのアドバイスとしては、そこまでしなくても世の中もっとテキトーに平和に、無関心に出来ていると思うのだが。「時代が違うんだよ、おっさん」というツッコミもあるかもしれないが、同居している長女や会社の若手も見ていても、そこまで「生き急いでいる」様子は見受けられない。
ちなみに長女や会社の若手に、「倍速視聴したことがあるか?」と聞いてみたが、全員の答えが「NO」であった。サンプルが少なすぎるのと、世代が少し上なのかもしれない。
確かにネットの無かった我々の学生時代と異なり、現在は膨大な情報に晒されているのは紛れもない事実である。しかし、若者のすべてがその情報に流されている訳でもないのでは?と感じる。この辺り、本書に書かれている内容が世の中のどれぐらいの割合を反映しているのかは、冷静に判断する必要があるのだと思う。
関連記事:「ファスト教養」